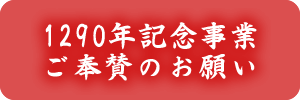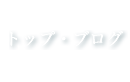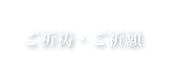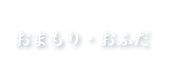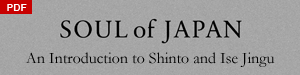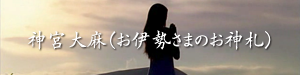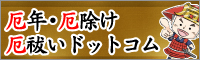-
最近の投稿
- 【 猫の日 ✕ ひな飾り 】 2026年2月17日
- 【 みんなでお祝いする豊かさ 】 2026年2月17日
- 【 この二日間限定 】 2026年2月17日
- 【 現代の神話 】 2026年2月17日
- 【 二万の和 】 2026年2月14日
記事の検索
記事カテゴリー
更新カレンダー
過去の記事
「塩梅」 由来は雅楽からシリーズ④
本日も昨日と同様、晴れてはいるものの肌寒い気温でした。
日中帯は青がキレイに映える快晴で、
お出かけ日和の一日となっています。
しかし今年の春は安定しませんね。
明日からはまた少し下り坂になるようです。
さて、雅楽が由来となっている日常語を
シリーズでこれまでご紹介していますが、今回は
雅楽が由来の日常語「塩梅(あんばい)」をご紹介します。
ほどよい加減の時に用いられる言葉で知られている「塩梅」。
一般には、料理で塩と梅酢の加減からきたと言われていますが
じつは古来より、雅楽においても
篳篥(ひちりき、雅楽で用いる縦笛の一種)の奏法の一つに
「塩梅」という呼び名があるのです。
※雅楽での正式な読み方は「えんばい」
この奏法は、指の押さえ方を変えずに
同じ孔(穴)の音でも吹き方を加減することで
音に幅を出し、音の高さを変えて吹く奏法であり
雅楽の旋律を特徴づける方法となります。
篳篥では、この塩梅が上手いくととても良い演奏なります。
そこで、ほどよい加減のことを「あんばいがよい」と
言うようになったとされているのです。
ちなみに、「塩梅」は
一つの音から次の音に移るとき、
いったんなめらかな音に下げてからすっと上げます。
この時、指孔を変えずに律を下げて吹くことを「メリ」と言い、
正律で力強く吹くことを「ハリ」と言います。
もうおわかりでしょうか。じつは
この「メリ」と「ハリ」は
「メリハリが利く」の語源にもなっているのです。