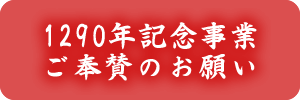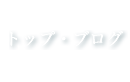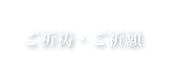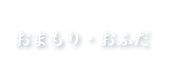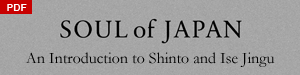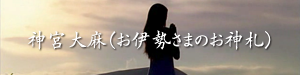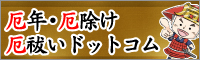-
最近の投稿
- 【 切り絵御朱印:陽華 】 2025年7月14日
- 【 この二日間限定 】 2025年7月12日
- 【 ご神気をお手元に 】 2025年7月12日
- 【 ツミ・ケガレの浄化 】 2025年7月12日
- 【 お待たせしました 】 2025年7月12日
記事の検索
記事カテゴリー
更新カレンダー
過去の記事
【平成23年 年越の大祓式】12/25(日)15時~
日本漢字能力検定協会から
今年、平成23年(2011年)の世相を1字で表す
恒例の「今年の漢字」が「絆」に決まったと発表されました。
「絆」が選ばれた理由としては、
東日本大震災や紀伊半島豪雨などで
家族や仲間との絆の大切さを改めて知ったことや、
サッカーW杯で優勝した「なでしこジャパン」の
チームワークなどが挙げられたそうです。
ちなみに、2位が「災」、3位が「震」、4位が「波」、
5位が「助」と、震災を連想させる漢字が続いています。
皆さんにとっての「今年の漢字」は何だったでしょうか。
さて、毎年、年に二回行われる大祓ですが
12/25(日)15:00~「年越の大祓式」を斎行いたします。
ご自由にご参列できますので、どうぞご参集ください。
ご参列できない方も
社頭にて事前に人形(ひとがた)を頒布しますので、
大祓人形をお持ち帰りいただき、当日12/25までに社務所へお納め下さい。
その年々の節目におこなわれる大祓は、
自らの罪や気枯れを祓うとともに、
今年の自分を振り返るための機会としたいものです。
■大祓式とは
私たちが日常生活の中で知らず知らずのうちに人を傷つけたり、
罪を犯したり、穢れに触れています。
そして、その状態を放っておくといずれ大きな災厄となって
降りかかってくると云われています。
この大祓式の神事は
それらの「罪」「過ち」を取り除き、
体内に生じた「けがれ(=気枯れ)」を人形(ひとがた)に託して
祓い除けるという日本古来の伝統的な行事です。
毎年6月と12月の末に行われ、6月を「夏越の大祓式」、
12月を「年越の大祓式」といいます。
■歴史
その歴史は古く、平安時代に大宝律令で正式な宮中行事と定められ、
中世より全国に普及し、現在も多くの神社で行われています。
■人形(ひとがた)
大祓では、身代わり人形に託して、これまでの罪穢れを祓い除けます。
①各人それぞれが自身の全身を人形で丁寧になでます。特に病ん
でいる部分などがあれば、より丁寧になでるとよいでしょう。
②最後に、その人形に「フーッ」×3、と息を3度吹きかけます。
こうすることで、
自分に積もっている罪や穢れ、身体の悪い部分が人形に移ると云われています。
それらが人形に乗り移るよう祈念を込めましょう。
年の瀬も間近になりました。
大祓式により、清浄な心身で残りの新年を迎えましょう。
新年に向け、新たな試みを準備中
師走を感じる寒さではありますが、
比較的穏やかな天候に感じられる一日でした。
週間天気予報によると、
しばらく同じような天気が続くようです。
さて、新年の準備に追われる毎日が続いていますが
平成24年を迎える今度のお正月から、新たな試みとして
神社からのお知らせやメッセージを “形” としてお届けしたい
と思い、神社からのお便りである「社報」を現在製作中です。
予算の都合もあり簡単な作りではありますが、
今回の第一号には
「日本の心」、「日本人にとってのお正月」、
「平成24年の人生儀礼・年齢早見表」などを盛り込んでいます。
初詣の参拝者の方々に社頭で配布したり、
新年のご祈祷を受けられる方々にお渡しする予定です。
まだまだ完成には手がかかりそうですが、
時間の猶予も残り少なくなってきているので
ピッチを上げ、なんとか新年には間に合わせなければなりません。
参拝される方々の心に響くようなものができればと思いますが、
果たしてどのようなものになりますでしょうか。。。
平成24年「戌の日」 安産祈願
今年も残すところあと二十日間ほどとなりました。
諫早の街中でもいたるところで
クリスマスや年末、新年に向けての準備が感じられます。
今年の「戌の日」は
12月21日(水)の一日を残すのみとなりましたので、
今回は来月以降、平成24年の「戌の日」をご紹介したいと思います。
ご存じのように、安産祈願は日本古来の習わしにより
妊娠5ヶ月目頃の「戌の日」に、妊娠された奥様のご健康と
お腹の赤ちゃんのすこやかな成長をご祈願するものです。
そもそも安産祈願(着帯祝い)とは、妊婦のお腹に木綿の布で作られた
腹帯(ふくたいorはらおび、岩田帯(いわたおび))を巻いて、
安産と母子の無事を神社などに参詣し祈願することを言います。
安産祈願を、妊娠5ヶ月目頃の「戌の日」におこなうのは
犬はたくさん子を産み、その上お産が軽いことから
古来より安産の守り神として人々に愛されてきたことにあやかったものです。
腹帯は、妊婦に母親となることへの自覚を高めさせる趣旨があると同時に、
胎児を保護し胎児の霊魂を安定させる意味もあると言われています。
ただ、ご祈祷の時期は
必ずしも妊娠5ヶ月目の「戌の日」でなくとも構いません。
体調が不安定な場合は「戌の日」にこだわる必要はありませんし、
お身体の安定している時期であれば
ご都合のつかれる佳き日を選んでお申込みいただいて結構でございます。
下記に平成24年「戌の日」一覧をご紹介します。
ご懐妊の方は、安産祈願の
時期の目安としてご参考くださいませ。
■平成24年(2012年) 戌の日一覧 ※ご参考
1月 2日(月)、14日(土)、26日(木)
2月 7日(火)、19日(日)
3月 2日(金)、14日(水)、26日(月)
4月 7日(土)、19日(木)
5月 1日(火)、13日(日)、25日(金)
6月 6日(水)、18日(月)、30日(土)
7月 12日(木)、24日(火)
8月 5日(日)、17日(金)、29日(水)
9月 10日(月)、22日(土・祝)
10月 4日(木)、16日(火)、28日(日)
11月 9日(金)、21日(水)
12月 3日(月)、15日(土)、27日(木)
伊勢神宮新穀感謝祭参宮団
先日、伊勢神宮新穀感謝祭の参宮団に参加して参りました。
式年遷宮の準備が進んでいることもこの目で確認できましたし、
外宮・内宮の特別参拝や神楽奉納も初めて体験しました。
昨年は、年間の参拝者が880万人を超えたということで、
今回の参拝時にも全国から多くの方々がいらっしゃっていました。
また、長崎からの参宮団の皆様には
道中お世話になり大変ありがとうございました。
おかげで楽しく充実した「お伊勢まいり」が出来ました。

正式参拝をした談山神社の十三重塔

改修中の拝殿・本殿

談山神社の社号標

内宮の宇治橋前

正式参拝後いよいよ神楽殿へ

新穀感謝祭の直会
師走12月1日「つきなみさい」
平成23年もあと一ヶ月を残すのみとなりました。
新春を迎える準備のスピードを上げなければなりません。
さて、本日12月1日も定例の「つきなみさい」が執り行われました。
境内清掃のお手伝いを頂きました方々、
ご参詣いただきました皆様ありがとうございました。
次回の「つきなみさい」は
12月15日(木)
9:30~
となります。
皆様とともに
日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願します。
自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
なお、当日は月次祭に先立ち境内清掃を行います。
お時間ある方は、9時00分~9時15分までの間
清掃にご協力頂けますと幸いです。
また、月次祭に参列できない方も
月の始まり(一日)や中日(十五日)の節目には
各々のご都合のつく時間で結構ですので、
地元の氏神様をお祀りする神社へ足を運び、
社頭で心静かに参拝されることをお奨めします。
今ここに生かされていることへの感謝の気持ちを神様にお伝えしましょう。
■師走(12月)歳時記
誕生石:ターコイズ
誕生花:カトレア
開花:ポインセチア、トキワラン
青果:サトイモ、レンコン、ブロッコリー、ヤマイモ
旬魚:クロマグロ、ムツ、ナマコ、ホッキガイ
新春の巫女募集は受付終了しました
ホームページなどで告知をしていました
平成24年お正月の「新春奉仕の巫女さん 募集」の件ですが、
書類ならびに面接による選考により定員となったため、
締切を待たずに応募受付を終了させて頂きました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
今回ご縁がなかった方も、
次年以降も募集する予定ですので、
新春の神明奉仕にやりがいをお感じであれば
またの機会に応募いただけますと幸いです。
来年も11月上旬あたりから募集を開始するつもりです。
ユネスコ無形文化遺産 新たに二件登録
ここ数日は比較的あたたかく穏やかな天候が続いており、
過ごしやすさを感じながら日々社務に励んでおります。
さて、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の政府間委員会は
11月27日、日本が提案していた
「佐陀神能」と「壬生の花田植」について、
無形文化遺産に登録することを決めたという報道がありました。
佐陀神能(さだしんのう)は、
島根県松江市鹿島町の佐太神社とその近隣諸社で
約400年前から伝わる神楽で、
「七座(しちざ)神事」、祝言舞の「式三番(しきさんばん)」、
着面の神話劇である「神能」の三部から構成されています。
壬生の花田植(みぶのはなたうえ)は、
広島県北広島町に伝わる伝統行事で、
田んぼで稲を守護する田の神を祀り豊作を祈願するものです。
美しく着飾った人や牛、
早乙女と呼ばれる女性たちがお囃子の音色に合わせて、
歌をうたいながら苗を植えていきます。
いずれも1976年に
国の重要無形民俗文化財に指定されていましたが、
今回、長い時間をかけ世代を超えて受け継がれてきた
「生きた遺産」を保護するユネスコの無形文化遺産に
登録されたものです。
国内の登録件数は、今回の2件を含めると20件になるそうです。
残念ながら、現在の諫早神社には
無形文化遺産となるような行事は残っていませんが
昭和初期までは、「射手馬(いてうま)」と言われる
流鏑馬のような伝統行事が例大祭時に盛大に行われていました。
数百年に渡って続けられていたにもかかわらず、
その当時には諸々の事情があったのでしょうが、
途切れてしまったことは残念でなりません。
このような伝統行事やお祭りは
一度中断してしまうと、また復活しようと思っても
極めて難しくなるのが現実です。
各地域での伝統行事やお祭りなど、
現在は少子化などで継続することが難しくなっている
ということをよく耳にしますが、
なんとか知恵を絞って、また色々な方の手助けを得て
ぜひ「続けて」ほしいと強く願います。
私たちは、これまでの祖先がいて初めて存在し、
また未来を生きる人たちは
今の私たちがどのように時代を全うするかで
まったく違う世界になるのです。
私たちは、今を生かせていただいているだけであり、
私たちの中には過去や未来も共存しているんだという自覚を持って、
様々な判断をする必要があるのだろうと思います。
高校生の募集は定員達しました
先日のブログなどで紹介している
「新春奉仕の巫女さん 募集」の件ですが、
高校生の募集は定員となったため受付を終了させて頂きました。
昨日も応募の電話を頂きましたがその旨をお伝えしました。
せっかくのやる気のある方にお断りするのは
心苦しく本意ではありませんが、どうぞご了承下さい。
来年以降も募集しますので、
またの機会に応募いただけますと幸いです。
来年も11月上旬から募集を開始する予定です。
なお、現在は
12/31夜の時間帯を含めたご奉仕ができる
大学生以上の方の応募をまだ受付しております。
募集要項を確認いただき、
やりがいを感じられた方はどうぞご応募下さい。
平成23年 諫早神社 新嘗祭
本日11月23日、神社総代様ご参詣のもと
諫早神社にて恒例の新嘗祭が滞りなく執り行われました。
また、宮中や全国各地の神社でも同じように新嘗祭が斎行されています。

お供えされた御初穂
戦後は祝日として「勤労感謝の日」になりましたが、
もともとは「新嘗祭」として収穫への感謝を捧げる日だったのです。
古くから稲作を営んできた日本人にとって、
秋の収穫の時期は一年で最も喜ばしいときです。
収穫した御初穂をご神前に捧げて、神さまに奉告し、
神さまのご加護に感謝するのが新嘗祭です。
その起源は古く、弥生時代にまで遡ると云われています。
これまで千年二千年以上もの間にわたって絶え間なく
時代を超えて続けられてきた新嘗祭を
今年も同じように斎行できたことは誠に喜ばしいことです。
今年は東日本大震災があったからでしょうか、
毎年のように当たり前にできることも
なんと有難いことなんだと改めて感じています。
ドイツ大統領が伊勢神宮に参拝
神社新報(第3093号)によると、10月26日に
ドイツ連邦共和国のクリスティアン・ヴルフ連邦大統領が
伊勢神宮を参拝されたそうです。
大統領は同行する日独両国の関係者などとともに
内宮・御正宮の内玉垣南御門前まで進んで
二拝二拍手一拝の作法で拝礼されました。
海外の要人の方々が伊勢神宮にご参拝される際は、
参拝後に記帳をされるそうですが、
不思議なことにそのほとんどの方々は、名前だけでなく
自発的に参拝の感想やメッセージを書かれるとのことです。
今回、ドイツのヴルフ大統領も
以下のような内容で記帳をされています。
「人生において本当に大切なものは何か。
伊勢神宮というこの特別な地においては、
それをはっきりと感じることができます。
貴国日本が、これからも自然との深い繋がりを
守っていかれますことを心から祈念しています」
また、日本ドイツ両国の
良好な関係を願う旨も合わせて書かれたそうです。
このような感想やメッセージをお聞きすると、
私たち日本人が慌ただしい日常の中で忘れがちな大切なことを
ハッと気付かされる思いがします。
忙しい毎日の中でも、節目節目には
私たちの祖先が大切にしてきた日本人としての生き方を
見つめ直し、その意味を理解することも大事なのかもしれません。