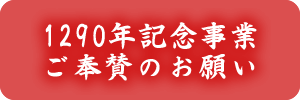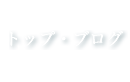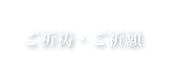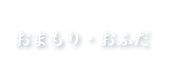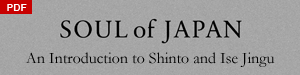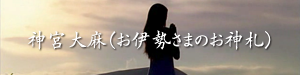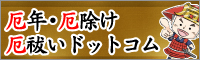-
最近の投稿
- 【 二万の和 】 2026年2月14日
- 【 勾玉の御朱印 】 2026年2月14日
- 【 2/11 おむすびでお祝い 】 2026年2月14日
- 【 2月の花鳥風月 season 6 】 2026年2月14日
- 【 あふれる御神威 】 2026年2月14日
記事の検索
記事カテゴリー
更新カレンダー
過去の記事
長崎県神社庁の復興祈願祭
ここ数日、朝晩は涼しさを感じるものの
日中帯は夏が戻ってきたかのような暑さの厳しい日が続いています。
さて、去る9月6日に長崎県神社庁主催で
県内神職や各地の総代さんによる
「東日本大震災復興祈願祭」が執り行われました。
これは毎年開催している
県内神社関係者の研修会日程の中で行われたもので、
私を含め200名以上の方々が参列されました。
参列者全員で黙とうを捧げ、復興祈願祭詞を奏上し
代表者の方々による玉串奉奠を行い、
復興祈願の神楽舞奉納もありました。

東日本大震災では、なんと約4,800社もの神社が
地震や津波の被害を受けています。
会場には被災した神社のパネル写真も数十点展示されており、
その範囲の広さと深刻さを改めて痛感させられました。
復旧復興が一日も早く前に進み、
被災された地域の皆様に元気になっていただけるよう
お祈りするとともに、できることをやっていこうと思っています。
翌日の地元・長崎新聞にも
この復興祈願祭の模様が紹介されていました。
↓

いさはやサマーフェスタ2011
昨日の天気予報では雨の確立が高いということでしたが、
幸いなことに朝から晴天に恵まれ、
地鎮祭のご奉仕も滞りなく務めさせて頂きました。
さて、本日は
毎年恒例となっている「いさはやサマーフェスタ」が
諫早市・多良見のぞみ公園で行われます。
今年も著名人として、篠原ともえさんや中村中さんが出演されます。
夏の終わりを迎えるこの時期に、
風が心地よい野外で音楽を満喫してみてはいかがでしょうか。
無料シャトルバスなども出ていますので
お時間ある方は、足を運ばれてみて下さい。
■日時
平成23年9月10日(土)
14:00~20:30頃
■場所
多良見のぞみ公園(諫早市多良見町木床106)
無料駐車場: 約100台
※雨天の場合は、多良見のぞみ会館
■タイムスケジュール
14:00開演 おおくまいちろう(司会)
14:00~16:00 サマーフェスタ親子イベント(こどもイベント広場)
【一般参加パフォーマー 】
14:00~14:20 1 ジュニア3Bダンシング・キッズ
14:30~14:50 2 東 啓司
15:05~15:25 3 THE☆HONEHONEROCKS
15:40~16:00 4 DIGGING UP
【プロアーティスト 】
16:30~17:00 5 THE TON-UP MOTORS
17:15~17:45 6 BAZRA(バズラ)
18:00~18:40 7 ザ・マーキュリーサウンド
18:55~19:55 8 「篠原ともえ+中村 中
with スティーヴ・エトウ、友森昭一」
20:00~20:30 9 無料抽選会
なお、無料抽選会は
「液晶テレビ」「空気洗浄機」「ポータブルDVDプレーヤー」など
豪華景品が当たり、その他にも賞品を67個用意しているそうです。
詳しくは、こちらのホームページからどうぞ。
「face isahaya」133号に
長崎地方も風が強い時間もありましたが、
台風12号は、紀伊半島をはじめ広域にわたって
大きな被害をもたらしています。
現在は温帯低気圧となり日本海に抜けたものの、
まだまだ局地的に大雨が続いている所があるようです。
さて、諫早のフリーペーパーで
「face isahaya」という情報誌があり、
最新133号の50ページ目に諫江八十八ヶ所巡りが
紹介されていて、その記事内に諫早神社のことが記載されていました。
諫江八十八ヶ所巡りとは、江戸時代後期の文政年間に
領内安泰や子孫繁栄などを願い弘法大師像を建立することを発願、
それから四年の歳月を経て、四国八十八ヶ所霊場になぞらえて
諫早領内の八十八ヶ所に其々勧請されたものです。
じつは、その諫江八十八ヶ所霊場の「第一番札所」は、
はじめ神仏習合の諫早神社(四面宮)の境内にありました。
しかし、明治の神仏分離令により、
四面宮の隣にあった五智光山荘厳寺が壊されてしまい、
「第一番札所の弘法大師像」も四面宮境内地から
現在の宇都墓地内に遷座されてしまったのです。
諫早神社は、
神仏分離の明治以前と以後で、あるいは
鳥居など様々なものが流された諫早大水害以前と以後では
すっかり様相が変わってしまったという悲愴な歴史があります。
それから長い年月が経ちますが、
まだまだその被害を引きずっていて復興したとは言えず、
お祀りしている大神様に対し大変申し訳なく思っており
これからも少しずつ元の姿に戻していかなければと思っております。
話は変わりますが、
faceに目を通している中で少し気になることがありました。
7月に行われた諫早万灯川まつりに参加した人から
諫早のいいところ・わるいところを聞いているアンケートがあったのですが、
その中で、わるいところはないという声が多かったものの、
「買い物するところが少ない」という趣旨の声も多く目についたことです。
これは少し気になります。
たしかに、買い物をするところの絶対数が少ないというのは
大都市と比べると当然そうなります。
また、諫早のような中規模の地方都市が
大都市を目指し、真似るようなことをやったとしても
未来永劫かなわないでしょう。
それよりも、諫早の特長を活かし
大都市には真似のできないような道を目指さなければ
これからの厳しい社会を生き残ることはできません。
ただ、そういう道を歩むためにも
時代の変化に対応したインフラが整備されていなければなりません。
その意味では、
たとえば現在の車社会にインフラが対応しきれているかというと、
必ずしもそうではないように思われます。
そういったことも克服していかなければなりません。
私は10年以上、東京で暮らしていましたが
比較しても、諫早には素敵なところがたくさんあります。
しかし、点在していて
自ら調べて見つけないと存在すら知らないかもしれません。
ですが、せっかく近くの地元に素敵なところがたくさんあるのですから、
それぞれの人がまずは地元のことをよく知ろうとすることが
第一に大切なことなのだと思います。
河上神社「風神祭」 二百十日と防災の日
本日は、日本に上陸しつつある台風12号の影響か、
晴れ間の覗く空模様ながら風が強い一日となっています。
さて、昨日は諫早神社での月次祭の後、
森山の兼務社・河上神社に移動し「風神祭」をご奉仕しました。
この「風神祭」は、
台風等が近づきやすいこの時期に、その難を免れますように
と祈願するものです。
昨日は、立春から210日目を数える
季節の移り変わり目のひとつで
台風等が来て天気が荒れやすいとされる「二百十日(にひゃくとうか)」でした。
農業に携わる方々にとっては特に「忌日」とされています。
また、9月1日は「伊勢湾台風」や「関東大震災」が
発生した日でもあり、一般的には「防災の日」としても知られています。
実際、今年は大型の台風12号が日本に接近しており、
古来からの言い伝えは大切にし引き継いでいかなければなりません。
幸い、長崎・諫早地方には
台風12号の影響はあまりないとされ、そのように願いますが、
大型で速度の遅い台風は、日本の広域にわたって影響を及ぼしそうです。
また、近年は
台風だけでなく、先週8/23夜に諫早を襲い
様々な被害を及ぼした豪雨のように
突発的で集中的な激しい雨が発生することがありますので、
普段からの注意が必要です。
長月9月1日「つきなみさい」
さて、9月1日も
定例の「つきなみさい」が執り行われました。
ご参詣いただきました皆様ありがとうございました。
次回の「つきなみさい」は
9月15日(木)
9:30~
となります。
皆様とともに
日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願します。
自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
なお、月次祭に先立ち
9時より境内清掃を行いますので、お時間ある方はご協力下さい。
■長月(9月)歳時記
誕生石:サファイア
誕生花:リンドウ
開花:キク、キキョウ、ヒガンバナ
青果:カボチャ、シイタケ、サツマイモ、クリ、ナシ
旬魚:サンマ、サケ、マイワシ、イボダイ、カマス
日本のトップが三日間で決まってしまう構造の欠陥
8/23夜の集中豪雨後、一転この一両日は晴天が続いており
今後しばらくは天候に恵まれるようです。
さて、今まさに
私たちの国の新しいトップが選ばれようとしています。
選ぶ期間は、三日間。
繰り返しになりますが、選ばれるのは「日本のトップ」です。
しかも、世間から ○○ と言われた
直近のトップを選んできた方々の投票だけで。
新たな悲劇の始まりになるのでは、
そう直観的に感じる人も少なくないのではないでしょうか。
私は、この現象について
与党を構成する方々の問題というよりも
だれが政権を担おうとも
必然的に陥る構造的問題なのではないかと思っています。
これ以上のことは触れません。
ただ、今の構造では
どんな立派な志や素晴らしいものを持っていようとも
その当事者になった途端、不可避の蟻地獄に吸い込まれ
引き摺り下ろされることになってしまいます。
何をするにも一定の期間は必要でしょう。
基本的なチェック機能を保持しつつ、腰を落ち着けて
今やるべきことをしっかりやれるような体制がつくれる構造にしなければ
この負のスパイラルは乗り越えられないのではと思います。
変えるべきは、顔触れではなく、
構造(統治組織・機構を生み出すしくみ)そのものなのではないでしょうか。
しかし、その構造は
現在の政治の中でしか変えることができないだけでなく、
当事者にとって自己否定が想起される困難を伴うところが
極めて実現を至難のわざにしています。
このままでは
取り返しのつかない段階にまで達してしまいそうで、
漠然とした不安を通り越し、背筋が凍りつく心持ちです。
ながさきプレス9月号
前回ブログでも触れた
長崎のタウン情報誌「ながさきプレス」ですが、
最新9月号を購入したところ、
諫早・大村の特集がされていたのでご紹介します。
今回の9月号では特集1として、
ランチ特集ということで県内全域のオススメランチが
掲載されており、少々遠くに足を延ばしても食べてみたい
と思わせるお店がいくつかありました。

そして、別冊での特集として
諫早・大村のグルメをはじめファッションや雑貨店など
色々なものが紹介されています。

■特集2/ISAHAYA OMURA PRESS
・Shinkansen Project vol.05
・諫早・大村出身よかとこ討論会
・諫早と大村のものづくりをたずねて
・諫早/大村で探す絶品県央グルメ
・ISAHAYA OMURA FASHION NEWS
・BEAUTY SPOT
・スイーツ&手みやげ
・可愛い雑貨&インテリア
・ISAHAYA OMURA PRESS SNAP
行ったことのあるお店もありましたが、初めて知るところもあり、
誌面のボリュームが少ないのではと思うくらい
もっと見たいと感じるものでした。
なお、「ながさきプレス」は
県内の書店・コンビニ等で購入できます。
対談コーナーやスタッフさんのあとがきに、
諫早の土地柄として、
「温かい人柄」「ハートフルな町」というフレーズがありましたが、
住んでいるとまさにそのように感じることが多いです。
諫早は交通の要衝であり、素敵な場所やお店も多くある半面、
少々大人しいという気質も関係しているのか、
通り過ぎてしまう町と言われる人もいらっしゃいます。
そうならないよう、良さを把握し説明できるよう
まずは地元の人が自分の住んでいる地域の歴史や文化などを
きちんと知ることが大事なのかなと思います。
諫早神社傍のイタリアン 「アーリオ」
先日、諫早市を襲った大雨により
市内の各所でも様々な被害が出ているようです。
自然災害に対しては、防災対策はもちろんですが
それ以上に私たち一人一人の意識改革も大切なことです。
さて、諫早神社そばに
美味しいイタリア料理のお店があるので紹介します。
諫早神社裏に永昌東町公民館があるのですが、
その対面に佇んでいるお店が
「トラットリア アーリオ(TRATTORIA Aglio)」です。
私も時々お伺いしていますが、
いつも美味しく楽しい時間を過ごすことができます。
長崎のタウン情報誌である「ながさきプレス」にも
先日掲載されていたのでそれを紹介します。
--以下、転載-------------------

諫早神社の裏路地にある、イタリアカラーが映える
<アーリオ>。
黒板に書かれた定番のアラカルトから、季節の食材で作る
「本日のおすすめ」など、とにかくたくさんのメニューが揃う。
しかもどれも最高においしい。
だから何度も足を運んで、食べ尽くしたいくらい。
お皿いっぱいに盛られる豪快な料理。
地元の野菜をたっぷり使って、味付けはほとんどが
塩コショウという、シンプルなもの。
素材の味がしっかり伝わる料理だ。
コースは、2人で5000円。
シェフおまかせのシェアコースが3000円~用意されている。
--転載ここまで------------------
ランチはされていないので、
神社参拝後に行く機会はないかもしれませんが
すぐ傍ですので、ぜひ一度は足を運んでみて下さい。
できるだけ予約をして伺ったほうがよいと思います。
■店名
トラットリア アーリオ(TRATTORIA Aglio)
■TEL
0957-21-1730
■住所
長崎県諫早市永昌東町4-10
■交通手段
諫早駅から約300m
駐車場あり(4台)
■営業時間
17時30分~22時
■席数
12席
【ご案内】伊勢神宮新穀感謝祭 参宮団
昨晩の大雨により
一時は本明川も氾濫の恐れがあり警戒していましたが、
なんとかぎりぎりのところで難を免れたようです。
ただ、神社境内の排水が悪いため
参道や参拝者駐車場付近が大きな水たまりとなってしまい、
午前中はずっとその排水処理作業に費やされました。
諫早大水害の悲劇を繰り返さないためにも
今後はきちんとした境内排水計画を考えなければなりません。
さて、長崎県神社庁では
毎年12月に「伊勢神宮 新穀感謝祭参宮団」という
「お伊勢まいり」のツアーを企画しております。
ブログでもご紹介しているように、
近年は伊勢神宮を参拝する方も年々多くなっており
平成25年に行われる第62回の式年遷宮へ向け、
これからさらに多くなっていくものと思われます。
今年で第11回という節目を迎えるこのツアーは
一般的な御正宮前での参拝だけでなく、
外宮・内宮の特別参拝や神楽奉納ができるなど、
より充実した「お伊勢まいり」ができるのではないかと思います。
なお、特別参拝とは、一般の参拝客は入れない場所で
さらに内側の御正殿に近いところで
特別に参拝することができるというものです。
「お伊勢まいり」をされる方は
ぜひ特別参拝をしていただきたいと思います。
また、特別参拝ができるだけでなく
他の神社などへの参拝も日程に組まれており、
今年は「談山神社」での正式参拝や
「伊奈波神社」への参拝もできるツアーとなっています。
予算的にも良心的な設定となっていると思いますので、
ご関心あられる方はぜひ参加を検討してみてはいかがでしょうか。
■ツアー名
長崎県神社庁主催 第11回 伊勢神宮 新穀感謝祭参宮団
■旅行日程
平成23年12月4日(日)~12月6日(火)
■旅行代金
¥72,000(予定)
■募集人員
40名(最少催行人員:25名)
■申込締切
平成23年10月30日
■食事
朝2回、昼2回、夕2回
■添乗員
長崎空港(行き)→長崎空港(帰り)まで同行
■お問合せ
長崎県神社庁 TEL:095-827-5689
昔の諫早神社に関する情報ありませんか?
本日もどんよりとした雲が覆っており、
お盆前からの不安定な天候が続いているようです。
さて、当神社は
神亀五年(西暦728年)の創建以来、千二百数十年に渡り
地域の氏神様として鎮座して参りました。
現在は行われていませんが、
昭和20年頃までは流鏑馬に似た「射手馬(いてうま)」が盛大に行われ、
昭和40年頃までは神輿(みこし)の渡御(とぎょ)が行われていました。
この地域の伝統行事が途切れてしまった要因は
戦争や諫早大水害等と思われますが、
時折、その当時のことを知っている方にお会いし
様々なお話をお聞きするのですが、どのような手順で行われていたか
どうしても断片的な情報しか得ることができません。
また、明治初期まで諫早神社(当時は四面宮)横にあった
五智光山荘厳寺に関する情報も十分とは言えません。
平成40年(西暦2028年)には、
当地に鎮座し1300年という大切な節目を迎えますが
これまでに諫早大水害をはじめとして様々な大災害に見舞われ、
神社保管の資料が消失し、残念なことに
昔の諫早神社に関する情報が少ないのが現状です。
つきましては、もしお手持ちで
諫早神社に関する古い写真や文献などがありましたら、
ご連絡頂きたくお願い申し上げます。
お手数をお掛けしますが、ご協力の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。