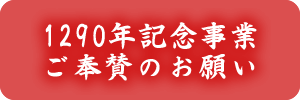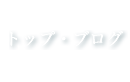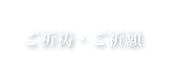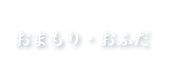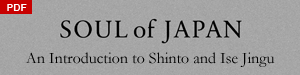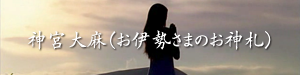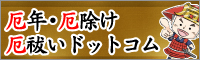-
最近の投稿
- 【 御朱印の貼り方ご紹介 】 2025年7月26日
- 【 大開運を手に入れる 】 2025年7月26日
- 7月24日は「大開運日」 2025年7月23日
- 【 きらめく特別御朱印 】 2025年7月23日
- 【 開運新月/晴風:せいふう 】 2025年7月23日
記事の検索
記事カテゴリー
更新カレンダー
過去の記事
諫江八十八ヶ所巡り・第一番札所
春の日に、突然冷え冷えとした日がやってくることがあります。
それを「花冷え」と言いますが、
ここ数日は全国的に「花冷え」とも言える天気となっています。
本日の諫早は晴天で気持ちのよい一日でした。
しかし、東京などでは最も遅い降雪として
41年ぶりの雪だったようです。
さて、「メディア掲載」ページにもアップしましたが
諫早ライオンズクラブから『諫江八十八ヶ所巡り』という本が
出版されました。
これは諫早市にある諫江八十八ヶ所霊場を詳しく紹介している
ガイドブックとなります。
諫江八十八ヶ所霊場は、江戸時代後期の文政年間に
領内安泰や子孫繁栄などを願い弘法大師像を建立することを発願、
それから四年の歳月を経て、四国八十八ヶ所霊場になぞらえて
諫早領内の八十八ヶ所に其々勧請されたものです。
じつは、この諫江八十八ヶ所霊場の「第一番札所」は、
初め四面宮(諫早神社)にありました。
しかし、明治の神仏分離令により
四面宮とともにあった五智光山荘厳寺が分離され、
「第一番札所の弘法大師像」も元々の四面宮境内地から
現在の宇都墓地内に遷座されてしまったのです。
近年はこの霊場を巡礼される方も多いそうですので
ご関心ある方は
諫江八十八ヶ所を巡拝してみてはいかがでしょうか。
卯月4月15日「つきなみさい」
ブログをスタートして
記念すべき100エントリー目の投稿です
本日も引き続き曇りの天気で
冬に戻ったかのような肌寒い一日となっておりますが
明日からは徐々に回復していくようです。
さて、本日の4月15日「つきなみさい」は
滞りなく斎行いたしました。
ご参詣いただきありがとうございました。
次回の「つきなみさい」は
5月1日(土)
9:00~
となります。
平日よりも早い時間となっておりますのでご注意下さい。
皆様とともに
日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願いたします。
自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
最後に、今後3ヶ月の「戌の日」をお知らせ致します。
安産祈願(着帯祝い)の時期目安としてご参考くださいませ。
4月 18日(日) 、30日(金)
5月 12日(水) 、24日(月)
6月 5日(土)、17日(木)、29日(火)
神宮大麻奉斎PR映像
本日は時おり日が差し込むものの
終日曇り空で
春を忘れてしまうほど肌寒い一日となっています。
明日もほぼ同じような天気となるようです。
さて、昨日のブログでは
「神宮式年遷宮PR映像」をお奨めしましたが、
本日は同様に本ホームページのトップ画面にリンクを張っている
「神宮大麻奉斎PR映像」をご紹介します。
「神宮大麻」とは
「天照大御神の御神札(大御璽)」のことで、伊勢神宮の御神札です。
伊勢神宮は、皇室の御祖神であり
私たち日本人の大御祖神である「天照大御神」をおまつりしています。
つまり、私たちの総氏神にあたり
最も貴いとされるお宮の御神札なのです。
![]()
太陽の光のように明るく恵み多きその御神徳は
様々な災厄から私たちを守り、生きる力をお与え下さるものです。
その広大無辺の御神徳を仰ぎつつ、家族や職場などの平安を願って
この「神宮大麻」をおまつりすることが大切です。
最近は住居スペースの都合により
神棚を設置するのが難しいケースもあるようです。
しかし、必ずしも神棚が必要ということではなく
御神札をおまつりし日々手を合わせ自分と向き合い
感謝の祈りを捧げることこそ大切と言えます。
「神宮大麻」など御神札のおまつりに関して
ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談下さい。
今回ご紹介する「神宮式年遷宮PR映像」は
あたりまえにある大切なものへ感謝することの意義を
素晴らしい映像美と音楽で表現しています。
感動的で魂を揺さぶられる作品かと思いますので
ぜひ一度、自然体でご覧になってみて下さい。
こちらからどうぞ(画像をクリック)
↓ ↓ ↓
また、現代の慌ただしく時が過ぎてゆく社会においては
自分と向き合ったり感謝をする時間を持ちづらい
趨勢となってきているのではないでしょうか。
先日放送された
フジテレビ開局50周年記念ドラマ「わが家の歴史」では
家族の家や職場のシーンに必ず神棚や御神札がおまつりされていました。
ご覧になられましたでしょうか。
また、昨日のテレビ東京系「ガイアの夜明け」では
コンビニチェーン・ローソンの社長さんが
朝出社した際、社長室におまつりしている神棚の前で
手を合わせお祈りしている様子が放送されていました。
このように、神棚や御神札をおまつりすることは
普段私たちが生活している中で忘れがちな
自分と向き合ったり感謝をする時間をもつ
大切なきっかけにもなるはずです。
神宮式年遷宮PR映像
本日は朝から
季節が逆戻りしたかのような肌寒い気温となっており
午前中は雨も降る曇り模様でしたが
午後からはなんとか持ち直しました。
残念ながら、明日も引き続き肌寒い一日となりそうです。
さて、諫早神社(四面宮)ホームページのトップ画面右下に
「神宮式年遷宮PR映像」のリンクを張っておりますが
ご覧になったことはございますでしょうか。
このPR映像は、
平成25年の第62回神宮式年遷宮に向けて、
神宮のことをより多くの人に深く理解していただくために
制作された映像を、Web用に再編集したものです。
神宮の清々しさと、そこにある生命力が
素晴らしい映像美と音楽で表現されています。
この映像を手掛けられたのは、クリエイティブ・ディレクターとして
活躍されているマンジョット・ベディ(1st Avenue代表者)
という方です。
JR東海「そうだ。京都へ行こう」のCMをはじめ
トヨタ自動車やNHKなどの仕事を手掛けられたことのある方です。
マンジョット氏は、インド・ニューデリーご出身で
外交官のお父様と世界を転々と回り、17歳のときに来日してから
日本に居住し、様々な経歴を経て
現在、広告業界で多方面に活躍されています。
今回の「神宮式年遷宮PR映像」も
本当に素晴らしい作品となっております。
本来であれば全篇を見て頂きたいのですが
短編のWeb版をぜひ一度ご覧になってみて下さい。
こちらからどうぞ(画像をクリック)
↓ ↓ ↓
「大仏開眼」NHK古代史ドラマスペシャル2
本日は暖かすぎると言えるほどの春の陽気で
お出かけするには
とてもよい土曜日だったのではないでしょうか。
ちなみに、本日は毎年この時期に斎行される
諫早小野金比羅宮・春例大祭の神事があり
小野地区を代表される多くの皆さまがご参集の中
厳かに執り行うことができました。
関係者の皆さま、お疲れ様でございました。
ここは参道が整備されていないため、
奥宮に到着するまでに足腰を使いますが
霊場として神域を感じさせる雰囲気の境内となっています。
さて、先日のブログでもご紹介した
NHK古代史ドラマスペシャル「大仏開眼」の後編が
本日放送されています。
諫早神社(四面宮)を創建された方でもある「行基」が
東大寺の巨大な大仏造営に携わった過程も描かれていました。
その時代(天平年間、西暦729年~)は
干ばつ・飢饉、凶作、地震、天然痘の大流行などが相次ぎ
惨憺たるご時世だったようです。
時の聖武天皇は、厳しい時代情勢の中にもかかわらず、
むしろそのような状況だからこそということもあるのでしょう、
大仏建立の詔を出されたのでした。
そして、この大事業を推進するために
幅広い人々の支持が必要であったということもあり
全国各地で民衆救済の活動をして広く人徳のあったものの
弾圧されていた「行基」の協力を得ることになったのでした。
しかしながら、残念なことに「行基」は
大仏の造営中にその生涯を終えることとなり
その完成を見ることはなかったのだそうです。
ちなみに、東大寺では
大仏創建に尽力した、聖武天皇、行基、良弁、菩提僊那を
「四聖(ししょう)」と呼び
東大寺を「四聖建立の寺」とも云うようになっています。
「幸せを運ぶ小さなおじさんの妖精?」
本日は昨日同様の晴天にもかかわらず
北風が強めで、体感気温の低い一日となっています。
全国的にもほぼ同様の天候らしく
夜桜見物には厳しいものになるかもしれません。
さて、テレビ東京系「やりすぎコージー」の
先月放送された「都市伝説スペシャル」において
たしか俳優・的場浩司さんやお笑い芸人・関暁夫さんが
お話されていた中で、
とある神社における奇妙な都市伝説の話がありました。
それは「関東地方のへそ」「関東の中心」とされる
とある神社(具体的な神社名は不明)で参拝をすると、
小さいおじさんの容姿をした妖精が現れるというものでした。
どれくらい小さいかというと
なんと「手のひらサイズ」くらいとのこと。
しかもその妖精は、幸せを運ぶ妖精なのだとか。
あくまで都市伝説ですので、にわかには信じがたいですが
本当にそんなことがあるのでしょうか。
じつは、的場さんは(本人曰く)
いろいろな場所で謎の生物に遭遇するなど、霊感が強いらしく
他の番組などでも多くの不思議体験を語っていらっしゃいます。
しかも、この話は
的場さん一人だけの体験ではなく
他の方もその神社で妖精の目撃したという話があるのだそうです。
的場さんは
その神社へ「しょっちゅう行く」のだそうで
最近はパワースポットとしても知られているようです。
複数の方々が見たことがあるということですが
あくまでも噂・都市伝説として
語られていることですので
「信じるか信じないかはあなた次第」です(笑)。
ちなみに、小人伝説といえば
諫早神社のご祭神である「少彦名大神」も
優れたお知恵と能力を兼ね備えている小人神として知られており、
「少彦名大神」は
あの「一寸法師」の原型・モデルと云われている神様なのです。
「千秋楽」 由来は雅楽からシリーズ③
春爛漫とはこのことを言うのでしょうか、
それくらい本日の空模様は
春らしく暖かく穏やかで過ごしやすい一日でした。
これからもこのような天候が続くといいのですが。
さて、先日のブログで
雅楽が由来となっている日常語がいくつかあるといういことで
「やたら」をご紹介しましたが、
今回そのシリーズの続きで
雅楽が由来の日常語「千秋楽」をご紹介します。
そもそも雅楽とは、日本古来の音楽や舞であり
完成された音楽体系を持ち、世界最古の合奏音楽として知られ
千数百年前から現在まで受け継がれているものです。
各地の神社・神楽殿で演奏が行われるなど
神社とも深い関係があります。
皆さんご存じのように
お芝居や相撲などの一つの興行期間の最終日のことを
「千秋楽」と言います。
この「千秋楽」も、雅楽が由来と言われており
後三条天皇か近衛天皇の時代の
大嘗会(だいじょうえ:即位の礼後に行う新嘗祭の宴)で
作られた「千秋楽」という曲があります。
この雅楽の曲(唐楽、管絃曲)は黄鐘調に移調される曲で
舞楽法会などの最後には
必ずこの曲を演奏したと言われています。
このことから
最終日のことを「千秋楽」と云うようになったのです。
雅楽が由来となっている日常語が他にもありますので
今後もこのシリーズを続けていきます。
「大仏開眼」NHK古代史ドラマスペシャル
本日は穏やかで温かな天候だったものの
時おり風が吹き、掃く量が
落ち葉の量に追いつかないという状況が続いています。
さて、本日4月3日(土)と来週4月10日(土)の全2回で
NHK古代史ドラマスペシャル「大仏開眼」が
放送されています。
今から約1300年前
混沌とした時代に、人々はどのような国を作ろうとし、
何のために東大寺の巨大な大仏を作ったのかということを
吉備真備、阿倍内親王(後の孝謙天皇)、藤原仲麻呂の
三人を軸にすえて描いている物語です。
本日は藤原氏の動乱から
聖武天皇が都を移すというところまでの物語でした。
その中で橋を造っている「行基」のシーンもありました。
じつはこの「行基」、
この諫早神社(四面宮)を創建された方でもあるのです。
「行基」はその当時、全国各地で民衆救済の活動をしており
数多くの墾田開発やドラマのシーンでもあったような
橋の造営などの社会事業に尽力をされた方です。
来週4月10日(土)19:30~の回で
いよいよ行基が大仏を造る過程が放送されるようですので
ぜひご覧になってみて下さい。
■主な出演者
吉備真備:吉岡秀隆
阿部内親王:石原さとみ
藤原仲麻呂:高橋克典
吉備由利:内山理名
橘諸兄:草刈正雄
行基:笈田ヨシ
光明皇后:浅野温子
聖武天皇:國村隼
卯月4月1日「つきなみさい」
本日は朝から雨の降り注ぐ天候となりましたが
午後からなんとか止んだようです。
ちょうど今は神社境内クスノキの葉が入れ替わる時期となっており
その落ち葉が容赦なく舞い降りてきます。
そのクスノキをよく見ると新芽が出ていました。
新たな命の息吹を感じるとともに生命の循環を見てとれます。

本日4月1日の「つきなみさい」は
滞りなく斎行いたしました。
ご参列いただきました方々には
お足元の悪い中ご参詣いただき、ありがとうございました。
次回の「つきなみさい」は
4月15日(木)
9:30~
となります。
皆様とともに
日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願いたします。
自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
■卯月(4月)歳時記
誕生石:ダイヤモンド
誕生花:ワスレナグサ
開花:サクラ、モクレン、ポピー、チューリップ等
青果:タケノコ、フキ、エンドウ等
旬魚:ニシン、アジ、タイ、アサリ
「いさはやリラックス」~まちあるきエリア~
本日朝には少し小雨が降ったものの
願いが通じたのでしょうか
その後はなんとかもちこたえてくれました。
明日からは徐々に天候は回復していくようです。
さて、諫早神社の鎮座する諫早市は
長崎県の県央部に位置しており
これまで交通の要所として進展してきました。
その諫早市から
市内の観光スポットや名産品、文化遺産などを紹介する
「いさはやリラックス」という
エリアマップ・パンフレットの配布がされています。
これは、市内観光の魅力や交流人口の拡大などのため
企画されたもので、公共施設や宿泊施設などに置かれているそうです。
このパンフレットでは市内を
まちあるきエリア、諫早湾エリア、森林浴エリア、
橘湾エリア、大村湾エリアという
5つのエリアに分類して紹介しています。
これからこの5つをそれぞれご紹介していきます。
今回はまず「まちあるきエリア」編です。
こちらでは諫早公園を中心とし
歩いて散策できる範囲のスポットが紹介されており
諫早神社も紹介されています。
主なものとしましては、
御書院・高城回廊、諫早公園・眼鏡橋、諫早市郷土館、諫早神社、
高城神社、御館山稲荷神社、安勝寺、慶巌寺、
天祐寺・諫早家墓所など、
諫早名物の食として、うなぎ、すっぽん、おこし、お酒などが
紹介されています。
他にも様々なスポット・食などが紹介されていますので
こちらの電子版「いさはやリラックス」を
ご覧になってみて下さい。
明日は「諫早湾エリア」をご紹介します。