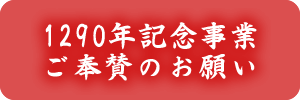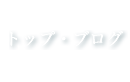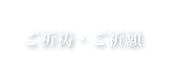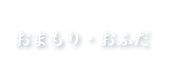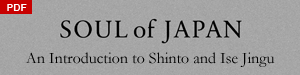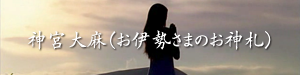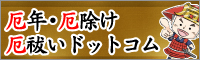-
最近の投稿
- 【 二万の和 】 2026年2月14日
- 【 勾玉の御朱印 】 2026年2月14日
- 【 2/11 おむすびでお祝い 】 2026年2月14日
- 【 2月の花鳥風月 season 6 】 2026年2月14日
- 【 あふれる御神威 】 2026年2月14日
記事の検索
記事カテゴリー
更新カレンダー
過去の記事
厄祓いの祈願章や御木神札について
本日の諫早地方は終日小雨が降り続き、
どんよりとした薄暗い雲に覆われた一日となりました。
予報によると、明日と明後日も雨の確立が高いようです。
さて、昨日今日は厄年祓いに来られた方々が多かったようです。
特に「厄入り」とされる年齢の方々については
お祓い後に、厄除け祈願章と御木神札(きふだ)をお渡ししています。
厄除け祈願章とは、厄入り専用の御守りでございます。
御木神札とともに一年間お祀りして下さい。
お渡しする際にもご案内していますが、
ご自宅に神棚があれば神棚の近くにお祀りし、
神棚がなければ、目線より高く清潔な場所にお祀り下さい。
棚の上など(できれば半紙などを敷いて)でも結構でございます。
方角としては、祈願章や御木神札の表が東か南を向くように、
人間から見ると部屋の北側か西側にお祀りします。
家の中でも、生活をする上でよく目にできるような部屋、
例えばリビングなどにお祀りするとよいでしょう。
そして、一年間お祀りして
翌年の「厄晴れ(厄明け)」でご参詣の際に
お守り頂いた感謝の心と共にこれらをお持ちになりお納め下さい。
神社にてお焚き上げを致します。
「厄入り」や「厄晴れ(厄明け)」、
あるいは「厄除け」などの厄年祓いを受けられる時期は
新年が明けて2月・3月頃までが多いようです。
なお、時期的にご都合があわない方も
厄年祓いは通年で承っておりますので3月以降でも結構です。
念のため、再度
今年の厄年祓い対象の方をお知らせ致します。
【平成24年(2012年) 厄祓い年齢:諫早を含む長崎地方】 ※数え年
■男
厄入 昭和63年生(25歳、満24歳)
厄晴 昭和62年生(26歳、満25歳)
厄入<大厄> 昭和47年生(41歳、満40歳)
厄晴<大厄> 昭和46年生(42歳、満41歳)
■女
厄入 平成6年生(19歳、満18歳)
厄晴 平成5年生(20歳、満19歳)
厄入<大厄> 昭和55年生(33歳、満32歳)
厄晴<大厄> 昭和54年生(34歳、満33歳)
初宮詣(宮参り) 絵馬の奉納
今日は立春です。
諫早地方は昨日よりは温かくなったものの、まだ春風とは言えません。
「暦の上では春」とされますが、
実際には寒さが厳しく 春本番が待ち遠しい時期です。
なお、二月=如月(きさらぎ)の由来は諸説あり、
「寒さを防ぐために着物を重ねることから衣更着(きさらぎ)とした」
という説と、
「陽気が良くなっていく時期であることから気更来(きさらぎ)とした」
という説などがあり、
どちらもまさしく二月の季節感を表していると言えるでしょう。
さて、新年が明けてから二月にかけては
寒さが厳しいということもあるのでしょうか、
初宮詣(宮参り)に来られる方が他の時期よりも少ないようです。
まだ暫らくは日によって寒さの厳しい時がありますので、
どうぞあまり無理をなさらずに、体調を整えてからお参り下さい。
なお、諫早神社では
初宮詣(宮参り)のお下がりとして絵馬をお渡ししています。
絵馬とは、神社に祈願または感謝の気持ちを表すために
願い事などを書いて奉納する額のことです。
お渡しした絵馬は、社頭右側の絵馬納め所の横に
台とペンがありますので、そちらで記入されてご奉納下さい。
初宮詣(宮参り)の絵馬ですから、
新たな命を授かったことに対する感謝の心と
これからの健やかな成長の 祈念を込めて
お書きになられご奉納いただければと思います。
今冬一番の冷え込み
今日の諫早地方は最低気温が氷点下となり、
長崎県全域でも観測史上最低の気温を観測するところもあり、
非常に冷え込みの激しい一日となりました。
報道によると、その寒さの影響で
路面凍結による事故や水道管の破裂などが発生しているとのことでした。
さて、今日は節分です。
神社の社頭にて一月中旬より頒布していた 節分用の福豆も、
ご用意していた分は全て出てしまったようです。
今日は、全国津々浦々のご家庭や神社で 節分の豆撒きが行われ
多くの方々が邪気を追い払い、福を呼び込まれたことと思います。
また、「そちらの神社で節分の豆撒きは行われますか?」
との問合せの電話も何件かいただきました。
残念ながら、今現在は神社として豆撒き行事は行っておりませんが、
将来的にはいつの日か、そういった節分の邪気祓いに関する
行事を復活したいと思っております。
如月2月1日「つきなみさい」
今日の諫早地方は朝から雨が降っておりましたが、
すぐに小康状態となりました。
気温も低い状態が続いており、インフルエンザが流行しているようです。
季節の変わり目ですので、皆さま十分にご自愛下さい。
さて、本日2月1日も
定例の「月次祭(つきなみさい)」が執り行われました。
小雨が降る中に、境内清掃のお手伝いを頂きました方、
ご参詣いただきました方々、ご参列ありがとうございました。
今日は節分も近いということで、お下がりとして
通常の「清祓の塩」と、節分用の「福豆」をお渡ししました。
次回の「つきなみさい」は
2月15日(水)
8:30~
となります。
※今年からは昨年までと時間が変更となり、
平日・土日祝とも原則8:30からの開式とします。
皆様とともに 日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願します。
自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
また、月次祭に先立ち境内清掃を行います。
お時間ある方は、8時00分~8時15分までの間
清掃にご協力頂けますと幸いです。
なお、月次祭に参列できない方も
月の始まり(一日)や中日(十五日)の節目には
各々ご都合のつく時間で結構ですので、
地元の氏神様をお祀りする神社や崇敬されている神社へ足を運び、
社頭にて心静かに参拝されることをお奨めしております。
今ここに生かされていることへの感謝の気持ちを神様にお伝えしましょう。
最後に、今後の「戌の日」をお知らせ致します。
安産祈願(着帯祝い)の時期目安としてご参考くださいませ。
如月 2月 7日(火)、19日(日)
弥生 3月 2日(金)、14日(水)、26日(月)
卯月 4月 7日(土)、19日(木)
前厄の厄祓い
昨日今日と、諫早地方は比較的穏やかな天気が続いています。
明日まではよい天候のようですが、
二月初日となる明後日は雪がちらつく予報となっています。
さて、ここのところ問合せが多い内容が
特に女性の方で、厄祓い(厄払い)の前厄の年齢の方々からのものです。
全国的な厄年としては、本厄があり
その前後の歳を前厄・後厄として、
計三年にわたって 厄祓いをするのが一般的です。
ただ、これは地域によって異なっているところもあり、
諫早を含む長崎地方では、地域の慣習として
「厄入り」と「厄晴れ(厄明け)」の計二年とされています。
ですが、同級生などで長崎を離れている方と厄年の話になったり、
本・雑誌やインターネットなどを見て、
じつは自分は前厄の年齢なのだと知ったため、心配になり
ご相談を受けるケースがあります。
そういった問合せの場合には、
「基本的には地域の慣習に則って行うものですが
もし気になるようでしたら、前厄のお祓いをお受けになるか
厄除けの御守りをお受けになられてはいかがでしょうか」
とお伝えしています。
念のため、今年の女性の前厄年齢をお知らせしておきます。
前厄 平成7年生(18歳、満17歳)
前厄<大厄> 昭和56年生(32歳、満31歳)
前厄 昭和52年生(36歳、満35歳)※37歳が本厄の地域
前厄の厄祓いをお受けになる方は、
特に大厄にあたる方で近年多くなってきているようです。
対象となる方で、気になられる方は
前厄の厄祓いを承りますのでご連絡の上お申込み下さい。
なお、諫早を含む長崎地方の慣習は以下の通りです。
【平成24年(2012年) 厄祓い年齢:諫早を含む長崎地方】 ※数え年
■男
厄入 昭和63年生(25歳、満24歳)
厄晴 昭和62年生(26歳、満25歳)
厄入<大厄> 昭和47年生(41歳、満40歳)
厄晴<大厄> 昭和46年生(42歳、満41歳)
■女
厄入 平成6年生(19歳、満18歳)
厄晴 平成5年生(20歳、満19歳)
厄入<大厄> 昭和55年生(33歳、満32歳)
厄晴<大厄> 昭和54年生(34歳、満33歳)
節分は「邪気祓い」→「福を呼び込む」
本日の諫早地方は最低気温が氷点下零度、
そして最高気温も5度ほどとなり寒い一日となりました。
明日は今日よりも幾分かは温かくなるようです。
さて、先日のブログで
2月3日の節分・豆撒きの方法などをご紹介しましたが、
近年はその日に「恵方巻き」を食べる習慣も広まってきています。
「恵方巻き」とは、節分の日に
その年の恵方を向いて、目を閉じて願い事を思い浮かべながら
無言で太巻き(恵方巻き)をまるかぶりすると一年間健康でいられるとされ、
食べ終えるまで口をきかず一気に食べるものです。
太巻き(恵方巻き)の中身は、
七福神にあやかって七種類の具を入れるなど
「福を食べる」「福を巻き込む」という意味合いもあるようです。
この慣習の由来は諸説ありますが、
江戸時代の商人たちが商売繁盛の祈願・験かつぎとして
始めたものと言われています。
ただ、全国に広まったのは近年で 、いわば新しい伝統と言えるでしょう。
恵方とは、その年1年の開運(吉方)の方角とされ
陰陽道に基づいて決められているもので
歳徳神(としとくじん、その年の福徳を司る吉神)が
いらっしゃる方角の事です。
よって、恵方はその年毎に変わっていきます。
例えば平成24年の恵方は北北西となります。
ちなみに、「恵方巻き」はあくまでも縁起もの、
つまり福を呼びよせるという意味合いはあっても
邪気を祓うという意味では「豆撒き」には及ばないでしょう。
2月3日「節分の日」は、季節の境目に当たり、
バランスが悪く、邪気が入り込みやすい日ですので
まずはしっかりと厄祓いを行ってから、福を呼び込みましょう。
平成24年「皇居勤労奉仕団の旅」ご案内
今日の諫早地方は時折り吹雪く天候となり、
非常に寒い一日となりました。
明日朝にかけて気温が低い状態が続くようですので、
路面の凍結などにはご注意下さい。
さて、長崎県神社庁では、天皇陛下御即位十年奉祝記念として
神社庁皇居勤労奉仕団をスタートし、
これまでに14回、約410名の有志の方々が参加されています。
皇居勤労奉仕とは、昭和20年5月に空襲で焼失した
宮殿の焼け跡を整理するため、有志が勤労奉仕を申し出たことで始まり
それ以降、奉仕を希望する全国の多くの方々により行われているものです。
現在の皇居勤労奉仕は、連続する平日の4日間、
皇居と赤坂御用地で除草,清掃,庭園作業などを行います。
長崎県神社庁では、 平成24年の今年も
第15回目の「皇居勤労奉仕の旅」を予定しており
現在、参加される方々を募集しております。
この皇居勤労奉仕は個人による申込みができず
一団体として宮内庁へ申請する必要があります。
(長崎県神社庁の奉仕団として申請)
ご関心あられる方は、 是非この機会に参加されてみてはいかがでしょうか。
なお、団体名簿を
半年前までに宮内庁へ届け出る定めとなっておりますので
(実施1ヶ月前まで変更可)、
日程・申込締切日は下記の通りとなっております。
●第15回 長崎県神社庁皇居勤労奉仕団
実施日:平成24年9月上旬~中旬(5泊6日)
募集人員:45名
申込締切:3月25日(宮内庁許可申請のため)
参加費:138,000円
簡単な概要のチラシは当宮にもございますが、
お問い合わせやお申込みなどは長崎県神社庁へお申し出下さい。
「おすくな社中」さんの参拝
今日の諫早地方は気温が上がらず、
終日凍えるような寒さを感じる一日でした。
天気予報によると、明日も雪が降るような寒さになるようです。
さて、先週の日曜日だったでしょうか
朝9時すぎ頃に、団体で諫早神社を参拝をされた方々がいらっしゃいました。
お聞きすると、「おすくな社中」という
少彦名神社を崇敬されている方々の団体だそうで
今回は「長崎のおすくな様を訪ねて」という企画で、
少彦名命をお祀りしている
長崎県内の神社を巡る旅をしている とのことでした。
少彦名命とは、諫早神社もお祀りしている神様で
そのご由緒は諸説ありますが
造化三神(ぞうかさんしん)のお子様とされ、
常世(とこよ)の国よりいらっしゃり、
小人神ながら 優れたお知恵と能力を兼ね備え、
大国主命(大己貴命)とともに日本の国造りをされた神様です。
体が小さく頭脳明晰であったということで、
昔話に出てくる一寸法師などのモデルとなった神様としても有名です。
その御神徳は、
特に医療、健康長寿、病気平癒をはじめ
農林水産業や商売繁昌などの守護神として崇敬されています。
当日は、雲仙のほうの神社を参拝されてから当宮に来られ、
その後は長崎市内の神社に行かれるとのことでした。
長崎だけでなく、全国各地の
少彦名命をご祭神としている神社を巡っておられるようです。
健康長寿や病気平癒のご利益が有名ということで
少彦名命を崇敬されている方々はさらに多くなってきています。
皆さまの「おこころ」が通じ、大神様のその御神威が益々高まり、
さらなる御神徳が発揮されることを祈念いたします。
「神社検定」が始まります
本日の諫早地方は日差しが眩しく青空が広がっていますが、
放射冷却の影響なのか、気温が昨日より4度ほど低くなっています。
そして明日から三日間は、時折り雪が舞い散るという予報で
気温がさらに低くなるかもしれません。皆さまご注意ください。
さて、数年前から
地域活性化のためのご当地検定や
マニアックと思われるような分野の検定など、
「○○検定」というものが数多く出てきています。
これまで「検定」というと
キャリアアップのため、あるいは特定の仕事に必要なので受験する、
といった種類のものが主流でしたので、
これまでとは少し位置付けが違ってきているのかもしれません。
このような時代の潮流の中で、
なぜこれまでなかったのだろうという思いもありますが
いよいよ第1回「神社検定」が始まります。
近年、日本の伝統文化であり日本人として心の拠り所である神社に
関心を持ち、参拝される方々が増えてきており、当宮でも
若年層を含め幅広い年齢層の方々が神社へお参りに来られています。
この「神社検定」は、
そういった方々に対して、正しい知識の啓発を図り
日本の伝統文化への理解を深めていただくため、
財団法人・日本文化興隆財団が主催し、神社本庁監修のもと行われます。
神社のことを正しく理解すると、これまでとまた違った心持ちで
お参りできるようになると思います。
今回は3級のみの受験開催となりますが、
平成25年からは2級、平成26年からは1級の検定も受験できるようです。
また、試験場所も全国各地にあり
他の検定試験よりも比較的多いため受験しやすいと思います。
日本の伝統文化や神社、そして日本人が育んできた「心」に
少しでも関心のある方はこの機会にぜひ受験されて下さい。
こちらの神社検定公式ホームページから申込みができます。
なお、申込みの受付期限もあるようですので、
お早めにお申し込み下さい。
以下、第1回「神社検定」 3級の実施概要です。
■試験日時
平成24年6月3日(日) 午前10時30分~
試験時間:90分 終了予定は12時15分
■試験会場
全国各地の試験会場にて(公式ホームページで随時掲載中)
■受験資格
学歴・年齢・性別・国籍等の制限はなし
■受験料
3級は 4,800円(税込)
その他詳細は公式ホームページでご確認下さい。


節分 福豆をお頒ちします 豆撒きの作法
本日の諫早地方は、風が時折り強いものの
温かな日差しが降り注ぐ空模様で、
気温も昨日までよりもぐっと高く感じた一日となりました。
さて、先日のブログでも告知していました
節分に向けた福豆の頒布について、改めてお知らせします。
ようやく準備が整いましたので、
先日より諫早神社の社頭にて福豆の頒布を始めております。
この福豆は、当宮において
邪気退散・無病息災のご祈祷を行ったものです。
各ご家庭での豆撒き用としてお使いいただけるもので、
節分の日までは神棚などにお供えしておいて下さい。
数に限りがありますので、ご希望の方はお早めにどうぞ。
また、ここで節分の豆撒きの作法についてご紹介します。
【 節分 豆撒きの作法 】
1.節分の日の夕刻までは、豆は神棚などにお供えしておく。
なぜ夕刻かというと、立春を控えたギリギリの時間を狙うためです。
2.節分の日の夕刻、まず玄関や窓を開けて
「鬼は外!」と(一般的には二回)言いながら
外に向かって豆を撒く。
最初に「鬼は外!」と言うのは、福を呼ぶ前に厄を祓うため。
3.続いて、家の中に向って
「福は内!」と(一般的には二回)言いながら
豆を撒き、福を招き入れる。
4.鬼が戻ってきたり、福が出ていかないように
玄関や窓をしっかりと閉める。
5.一年の無事や健康を祈り、豆を食べる。
また、年齢(できれば数え年)の数の豆を食べるといいとも言われている。
皆さん、このような節分の作法はご存じでしたでしょうか。
ちなみに、節分には福を取り込もうと「恵方巻き」や
「柊(ひいらぎ)に刺した鰯(いわし)の頭を門口に飾る」
という行事などもあります。
「恵方巻き」は近年普及した風習ですが、
後者の行事の由来は、昔からのもので
節分の夜には「かぐ鼻」という鬼が各家々を廻って
人を食べてしまっていたことがあり、
その鬼が嫌いな臭いの鰯で、柊の棘(とげ)とともに撃退するというものです。
節分の日に
このように多くの厄祓いの方法があるというのは、
それだけこの日が危うく、邪気が入り込みやすい日なのです。
皆さんもこの節分の日に、しっかりと鬼を退けて福を呼び込みましょう。