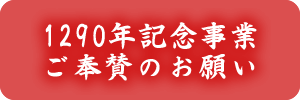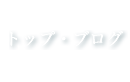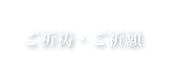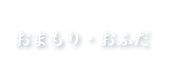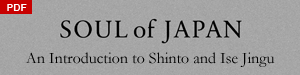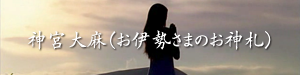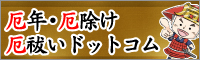-
最近の投稿
- 【 いざ、聖地へ 】 2025年8月2日
- 掲載されています 2025年8月2日
- 【 広がるご加護 】 2025年8月2日
- 【 8月の花鳥風月 season 6 】 2025年8月2日
- 【 季節を味わう 】 2025年8月2日
記事の検索
記事カテゴリー
更新カレンダー
過去の記事
「幸せを運ぶ小さなおじさんの妖精?」
本日は昨日同様の晴天にもかかわらず
北風が強めで、体感気温の低い一日となっています。
全国的にもほぼ同様の天候らしく
夜桜見物には厳しいものになるかもしれません。
さて、テレビ東京系「やりすぎコージー」の
先月放送された「都市伝説スペシャル」において
たしか俳優・的場浩司さんやお笑い芸人・関暁夫さんが
お話されていた中で、
とある神社における奇妙な都市伝説の話がありました。
それは「関東地方のへそ」「関東の中心」とされる
とある神社(具体的な神社名は不明)で参拝をすると、
小さいおじさんの容姿をした妖精が現れるというものでした。
どれくらい小さいかというと
なんと「手のひらサイズ」くらいとのこと。
しかもその妖精は、幸せを運ぶ妖精なのだとか。
あくまで都市伝説ですので、にわかには信じがたいですが
本当にそんなことがあるのでしょうか。
じつは、的場さんは(本人曰く)
いろいろな場所で謎の生物に遭遇するなど、霊感が強いらしく
他の番組などでも多くの不思議体験を語っていらっしゃいます。
しかも、この話は
的場さん一人だけの体験ではなく
他の方もその神社で妖精の目撃したという話があるのだそうです。
的場さんは
その神社へ「しょっちゅう行く」のだそうで
最近はパワースポットとしても知られているようです。
複数の方々が見たことがあるということですが
あくまでも噂・都市伝説として
語られていることですので
「信じるか信じないかはあなた次第」です(笑)。
ちなみに、小人伝説といえば
諫早神社のご祭神である「少彦名大神」も
優れたお知恵と能力を兼ね備えている小人神として知られており、
「少彦名大神」は
あの「一寸法師」の原型・モデルと云われている神様なのです。
いさはや つつじ祭り2010
午前中は雨も降ってきそうな曇りの天気でしたが
お昼前からはだんだんと晴れてきて
ぽかぽか陽気の一日でした。
さて、諫早の恒例のお祭りである
「つつじ祭り」が
今週4月10日(土)~4月18日(日)の期間、
日本歴史公園百選に選ばれている
上山公園(諫早公園一帯)で開催されます。
諫早公園は諫早神社から徒歩で約9分ほどです。
今年は例年と一味違って趣向を凝らした企画があるようです。
例えば、橋の下をくぐることができる
史上初の「めがね橋アーチ下の散歩道」や
参加自由の「めがね橋大合唱団」、
池の上で演奏する「めがね橋夜の音楽会」などです。
他にも、「じげもん料理の祭典」、「鰻まつり」、「ふるさと物産市」、
「フリーマーケット」、「露天商」、「健康いさはや21ウォーキング」、
「新緑スケッチ大会」、「ふれあい動物園」、「チャリティー春の茶会」、
「伊東静雄・詩の朗読会」、「囲碁フェスタ」、
「ウッドアート諫早作品展&即売会」など
多くの催しが開催されます。
春の陽気を感じながら
つつじの美しさをめでると同時に
様々な思い出を刻んでみてはいかがでしょうか。
イベント日時など
詳しくはこちらのチラシ(PDF)をご覧ください。
■問合せ先
諫早観光物産コンベンション協会
TEL:(0957)22-8325
「千秋楽」 由来は雅楽からシリーズ③
春爛漫とはこのことを言うのでしょうか、
それくらい本日の空模様は
春らしく暖かく穏やかで過ごしやすい一日でした。
これからもこのような天候が続くといいのですが。
さて、先日のブログで
雅楽が由来となっている日常語がいくつかあるといういことで
「やたら」をご紹介しましたが、
今回そのシリーズの続きで
雅楽が由来の日常語「千秋楽」をご紹介します。
そもそも雅楽とは、日本古来の音楽や舞であり
完成された音楽体系を持ち、世界最古の合奏音楽として知られ
千数百年前から現在まで受け継がれているものです。
各地の神社・神楽殿で演奏が行われるなど
神社とも深い関係があります。
皆さんご存じのように
お芝居や相撲などの一つの興行期間の最終日のことを
「千秋楽」と言います。
この「千秋楽」も、雅楽が由来と言われており
後三条天皇か近衛天皇の時代の
大嘗会(だいじょうえ:即位の礼後に行う新嘗祭の宴)で
作られた「千秋楽」という曲があります。
この雅楽の曲(唐楽、管絃曲)は黄鐘調に移調される曲で
舞楽法会などの最後には
必ずこの曲を演奏したと言われています。
このことから
最終日のことを「千秋楽」と云うようになったのです。
雅楽が由来となっている日常語が他にもありますので
今後もこのシリーズを続けていきます。
ノーベル化学賞・下村博士の銅像と講演
本日は曇り空の中にも
時おり光が差し込むような天候で穏やかな一日でした。
さて、平成20年にノーベル化学賞を受賞された
下村脩(しもむらおさむ)博士は、出生地こそ違うものの
ご両親とも長崎県のご出身であります。
お父様は雲仙市の出身で
お母様が諫早市長野町の出身です。
16歳の頃に、お母様のご実家(諫早市長野町)に疎開され
その後、現・諫早高校を卒業し
諫早市小野町にあった
旧制長崎医科大学附属薬学専門部(長崎大学薬学部の前身)で
学ばれています。
下村博士は青春時代を
この諫早の地で過ごされたということです。
先日、下村博士の過ごしたという家がまだ残っていると聞き
長野町にあるその家を見に行きました。
残念ながら長い間空き家となっていたようで
朽ち果てていましたが、とても大きな屋敷で
当時の面影を感じさせる佇まいでした。
このように下村博士は
諫早に非常に深いゆかりがあるということで
このたび諫早市役所近くの諫早高校正門前付近に
下村博士の銅像が建立されることとなりました。
銅像は既に完成し
明後日4月6日(火)11:00から除幕式が行われ
下村博士ご本人や
諫早市にお住まいの弟さんも参加されるそうです。
そしてその後14:00からは
諫早文化会館にて「ノーベル賞への道のり」と題した
下村博士の記念講演が行われるそうです。
こちらの記念講演は入場無料とのことですので
ご関心のある方は
諫早市から生まれたノーベル賞受賞者のお話を
聞かれてみてはいかがでしょうか。
「大仏開眼」NHK古代史ドラマスペシャル
本日は穏やかで温かな天候だったものの
時おり風が吹き、掃く量が
落ち葉の量に追いつかないという状況が続いています。
さて、本日4月3日(土)と来週4月10日(土)の全2回で
NHK古代史ドラマスペシャル「大仏開眼」が
放送されています。
今から約1300年前
混沌とした時代に、人々はどのような国を作ろうとし、
何のために東大寺の巨大な大仏を作ったのかということを
吉備真備、阿倍内親王(後の孝謙天皇)、藤原仲麻呂の
三人を軸にすえて描いている物語です。
本日は藤原氏の動乱から
聖武天皇が都を移すというところまでの物語でした。
その中で橋を造っている「行基」のシーンもありました。
じつはこの「行基」、
この諫早神社(四面宮)を創建された方でもあるのです。
「行基」はその当時、全国各地で民衆救済の活動をしており
数多くの墾田開発やドラマのシーンでもあったような
橋の造営などの社会事業に尽力をされた方です。
来週4月10日(土)19:30~の回で
いよいよ行基が大仏を造る過程が放送されるようですので
ぜひご覧になってみて下さい。
■主な出演者
吉備真備:吉岡秀隆
阿部内親王:石原さとみ
藤原仲麻呂:高橋克典
吉備由利:内山理名
橘諸兄:草刈正雄
行基:笈田ヨシ
光明皇后:浅野温子
聖武天皇:國村隼
詩吟(しぎん)
本日は終日穏やかな一日でしたが
関東では強風が吹き荒れ
交通機関がマヒするなどの大きな影響もでたようです。
さて、明後日4月4日(日)に
諫早文化会館にて「詩吟朗詠錦城会 長崎県本部大会」が
行われます。
詩吟とは日本の伝統芸能の一つで
漢詩や和歌、俳句、短歌などに独特の節回しをつけて
吟ずる(詠う)ものです。
最近は、漫才コンビ「天津」の木村卓寛氏が
「あると思います」「吟じます」というフレーズを使い
詩吟風のネタを披露しているため、そのような形のものを
耳にしたことがあるかもしれません。
詩吟の由来は古く、平安中期の頃の漢詩や和歌の
宮廷歌謡 「朗詠」であると言われています。
江戸時代になると
徳川五代将軍「綱吉」が、湯島に昌平坂学問所を開き、
諸藩の秀才を集めて全寮制の教育を行った(現在の東大の前身)時に、
漢詩の講義で、漢詩に「ふし」をつけて読んで聞かせたのが
今日の詩吟の始まりとなったと言われています。
また幕末においては、悲憤慷慨・士気高揚を図り
明治維新の原動力の一翼を担ったとも言われています。
近年は、老若男女だれでも気軽に始められるということと
腹式呼吸を使い心肺機能を健康にする効果があるということから、
健康維持などをきっかけに詩吟を始める方も多いそうです。
その詩吟の大会が
明後日、諫早文化会館で行われますので
ご関心のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。
■詩吟朗詠錦城会 長崎県本部大会
日時:4月4日(日) 午前11時~午後4時30分
場所:諫早文化会館・大ホール(長崎県諫早市宇都町9-2)
入場料:1,000円
問合せ先:詩吟朗詠錦城会長崎県本部(TEL:0957-26-8814)
なお、昨日のブログ記事の
卯月(4月)歳時記の内容が誤っておりましたので
訂正いたしました。
卯月4月1日「つきなみさい」
本日は朝から雨の降り注ぐ天候となりましたが
午後からなんとか止んだようです。
ちょうど今は神社境内クスノキの葉が入れ替わる時期となっており
その落ち葉が容赦なく舞い降りてきます。
そのクスノキをよく見ると新芽が出ていました。
新たな命の息吹を感じるとともに生命の循環を見てとれます。

本日4月1日の「つきなみさい」は
滞りなく斎行いたしました。
ご参列いただきました方々には
お足元の悪い中ご参詣いただき、ありがとうございました。
次回の「つきなみさい」は
4月15日(木)
9:30~
となります。
皆様とともに
日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願いたします。
自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
■卯月(4月)歳時記
誕生石:ダイヤモンド
誕生花:ワスレナグサ
開花:サクラ、モクレン、ポピー、チューリップ等
青果:タケノコ、フキ、エンドウ等
旬魚:ニシン、アジ、タイ、アサリ