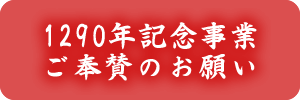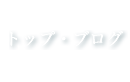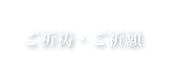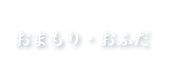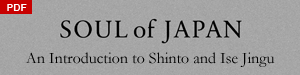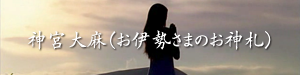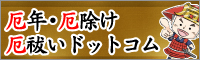-
最近の投稿
- 【 10月の花鳥風月 season 6 】 2025年10月8日
- 【 幸せを運ぶ 】 2025年10月8日
- 【 夜空を見上げて 】 2025年10月8日
- 11/15土【ピース文化祭2025】流鏑馬 2025年10月8日
- 【 三吉日が重なる奇跡 】 2025年10月6日
記事の検索
記事カテゴリー
更新カレンダー
過去の記事
長崎龍馬ライナーが運行開始
昨日は、透き通った海のように爽やかな青空で
暖かくすっきりとした一日でした。
本日も引き続き晴天が続いていますが
昨日と比べると若干肌寒いような気がします。
さて、本年より
長崎出身・福山雅治さん主演のNHK大河ドラマ「龍馬伝」
が放映されています。
皆さんご覧になられていますでしょうか。
今回その放映に伴い、JR九州では
JR大村線(長崎~諫早~佐世保間)を走る「シーサイドライナー」に
坂本龍馬の写真をあしらったラッピング電車、
「長崎龍馬ライナー」の運行を先週末から開始しました。
諫早神社の近く、JR諫早駅も停車駅となっています。
期間は本年12月末までの予定とのことで、
両数は200形車両2両(一編成)となります。
また、この「長崎龍馬ライナー」の運行を記念し
記念乗車券も発売されています。
こちらは4月30日までの期間で、発売額は900円
長崎駅ならびに佐世保駅での販売となるそうです。
種類は、
長崎発→450円区間(諫早)の2種類セット
佐世保発→450円区間(有田or川棚)の2種類セット
となります。
詳しくはこちらのニュースリリースをご参照ください。
どのようなデザインになっているのか気になりますね。
「長崎龍馬ライナー」
一度は乗車してみたいものです。
楽曲「神集い」
本日は、大安の日曜日ということで
多くの御祝い事が行われたことと思います。
諫早も早朝に小雨が降ったものの、
次第に天候が回復し、気温も暖かく
文字通りお日柄の佳い一日となったのではないでしょうか。
さて、本日のブログでは
諫早市出身の脚本家・市川森一さんが作詞を担当している
歌手・香西かおりさんの楽曲「神集い」をご紹介いたします。
市川森一さんといえば、多くの映画、
テレビドラマ、舞台の脚本などを手掛けておられるので
ご存じの方も多いと思います。
その市川さんもメジャーレコードの作詞は
今回が初めてとなるそうです。
じつは、楽曲「神集い」は
「女の帰郷」 というシングルCDのカップリング曲です。
「女の帰郷」 は、昨年9月23日に発売された
長崎県五島列島を舞台に綴られた楽曲で、
こちらも市川森一さんが作詞を担当されています。

「神集い」の歌詞は、なんと
古事記・日本書紀などの神話が題材となっておりまして
神様の名前などがたくさん出てくるユニークものになっております。
気になる方はこちらから歌詞をご覧になってみて下さい。
その曲調は意外にアップテンポで速いリズムとなっており
とても楽しい楽曲に仕上がっています。
残念ながら、試聴はできないようですので
ご関心あられる方は購入してお聞きになって下さい。
なお、明日は毎月1日15日に行っております
「月次祭」の日でございます。
ご自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
■つきなみさい
3/15(月) 9:30~
『とろける生カステラ』に抹茶味が登場
以前ブログにて紹介しました
諫早市にある菓秀苑森長の『とろける生カステラ』が
発売以来4ヶ月で
なんと1万個を超える販売を記録したそうです。
すごいですね。
現在は、百貨店の物産展への出店など
さらに人気が高まっているとのこと。
そこで今回、新たな試みとして
生カステラの新しい味を発売することが決まったそうです。
その第1弾は、抹茶味。
しかし、期間限定で
昨日3月8日~平成22年4月7日の一ヶ月間
インターネットでの販売となります。
宇治産の抹茶をふんだんに使用しているそうで
抹茶と、生カステラのあの食感とがコラボレーションすることで
どう美味しくなっているのか楽しみですね。
お求めはこちらからできます。
↓
http://store.shopping.yahoo.co.jp/moricho/index.html
http://www.rakuten.co.jp/kasutera-moricho/
地域活性化についての公開講座
諫早図書館で、としょかん友の会と
ビジネス情報支援図書館懇話会の企画により
「地域活性化における地域ブランドの構築」と題した
公開講座が3/6(土)に開催されるそうです。
神社にとっても
その地域の人々の幸せを願うことや地域活性化、
地域の発展は、大切なテーマの一つです。
これまでもこれからも神社は地域とともに歩んでいきます。
そのとき大切なことは、
単なる批判や消極的な姿勢ではなく、
前向きに皆で知恵を寄せ合っていくという心構えなのでしょう。
そういう意味でも、このような講座で
地域の人が自分の住んでいる地域について
前向きに考える機会があることはとても意義深いものと思います。
この企画は長崎県立大学地域公開講座の第二弾で、
事前の申し込みや参加費は「不要」とのことですので
ご都合つかれる方は
参加してみてはいかがでしょうか。
詳細は下記の通りです。
●演題:「地域活性化における地域ブランドの構築」
→地域活性化のひとつの方策としての地域ブランドについて。
地域にある資源をどのようにブランディングしていくのか
具体的事例をあげながら説明。
●講師:長崎県立大学 流通・経営学科准教授
山口 夕妃子氏
●日時:平成22年3月6日(土) 13:30~15:00
●会場:諫早図書館・視聴覚ホール
なお、明日は毎月1日・15日に斎行しております
「つきなみさい」の日でございます。
ご自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
■つきなみさい
3/1(月) 9:30~
「いさはやを撮ろう会」写真展
現在、アエルいさはや2F
まちづくり工房・ギャラリーホールでは
第一回「わが街いさはやを撮ろう会」の
写真展が開催されています。
これは、ふるさと諫早の風景を写真で撮り、
写真を通してまちづくりに貢献しようということで
「わが街いさはやを撮ろう会」が企画し、開催されているものです。

じつはここに諫早神社の写真も展示されています。
大きなパネルに
長崎県天然記念物に指定されているクス群をはじめ、諫早神社の境内を
様々な視点で撮った写真で複数組み合わせて展示しており、
とても綺麗な作品となっております。
制作された方をはじめ
関係者の皆様に深く感謝申し上げます。
見慣れている風景と思っていても
新しい発見や新しい魅力に気づくことができました。
皆さんもぜひご覧になって下さい。
他にも諫早各地を撮った作品が展示されており
この写真展を通じて
諫早の新しい一面を再発見してみてはいかがでしょうか。
なお、期間が
明日2/28(日)までとなっておりますのでご注意下さい。
時間は10時~21時です。
場所:アエルいさはや2F まちづくり工房ギャラリーホール
(諫早市本町3-11栄町アーケード内)
※駐車場は90分まで無料
【諫早の名所!?】フルーツバス亭
諫早市街から佐賀方面に向う
小長井町の国道207号沿いを中心に
フルーツをかたどったバス亭が設置されております。

フルーツバス亭(イチゴ)
最近は、このバス亭を目当てに
ドライブ中の家族連れの方々が車を停め
記念撮影する姿も多く見られるようで
いまや諫早の名所と言っても過言ではありません。
このフルーツバス亭は、平成2年に開催された
長崎旅博覧会をきっかけに設置されました。
年数も経過していることから
最近、外観を塗り直すなどリニューアルをしていて
色鮮やかなキレイな姿を見ることができます。(一部を除く)
フルーツバス亭は
小長井町に全部で16ヵ所設置されています。
国道207号沿いですと
長里駅近くの「殿崎」から「阿弥陀崎」までの間のバス停に
あるようです。
16全てのフルーツバス亭を見つけるのは
難易度が高いと言われているようですので
ご関心ある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。
通り名でえべっさんを探せ!
諫早市中地区町内会連合会などでつくる
「えべっさん実行委員会」では、
諫早に点在する「えべっさん(恵比寿像)」を歩きながら探し、
諫早のまちを再発見・再認識するイベント
「通り名でえべっさんを探せ!」の開催を予定しております。
諫早には、これまでの歴史と関連し
多くの恵比寿像があるそうです。
■通り名でえべっさんを探せ!
~ウォークラリーイベント参加者募集~
とき:平成22年2月28日(日) 12:30~ ※雨天中止
集合場所:諫早アエル前ポケットパーク
申込み期限:2月22日(月)必着 先着30名
参加費:無料
詳しくは、
国交省・長崎河川国道事務所ホームページの新着情報をご覧ください。
恵比寿様は、
幸福をもたらす七福神として知られており
特に西日本では、
「えべっさん」と親しみを込めてよばれています。
大きな鯛を抱えて釣竿を持っている姿の恵比寿像は有名で
全国各地にありますので
ご覧になったこともあるのではないでしょうか。
古来より、全国津々浦々で
海岸に流れ着いた漂着物や魚網にかかった石などを
エビス様の御神体として祀る風習などがあったようで、
もともとエビス様は海の向こうからやってくる神様として、
豊漁や海上安全などをもたらす神様として信仰されていました。
鎌倉時代の頃からは、福の神としてのご神徳が歓迎されて
各地の市場などに祀られるようになり
室町時代以降は、商業都市を中心に商売繁盛の神様として
多くの人々から盛んに信仰されています。
なお、東京の神田明神などでは
諫早神社のご祭神でもある少彦名命と恵比寿様が
習合(同一神と)されており、
商売繁盛、医薬健康、開運招福の神様として、
また、温泉を伝えた神様として知られております。
山下淵の大なまず その3
先日のブログ「山下淵の大なまず」の続きで
今回で完結となります。
【山下淵の大なまず その3】
さて、女性が姿を消したその翌日のこと。
山下淵に、見た事もないような
大なまずの死がいが浮かびました。
その話は町中に広がり、たちまち殿さまの耳にも届きました。
じつはその時代、山下淵では
魚を獲ることは固く禁じられていたのです。
家来が調べて見ると、大なまずの心臓に
一本の鋭いモリが突き刺さっています。
見るとそのモリには、
はっきりと『中村大蔵』という銘(めい)が刻まれていたのです。
「中村大蔵を、ひったてい!」
ただちに大蔵は縄をかけられて、お城の庭に引き出されました。
「なまずを殺したのは、自分でありません」
大蔵は言いましたが、
「では、誰が殺したというのだ?」
「それは・・・」
主との約束を破る事は出来ないので、仕方なく黙っていました。
「黙っておる所を見ると、やはりお前の仕業だな!
魚を取ってはならぬとの禁を破った上、罪を認めぬとは!
さっそく、処罰を与えてくれるわ!」
殿さまはかんかんに怒ってしまいましたが、家来の一人が、
「殿、お待ち下さい。
モリを作ったのは、確かに大蔵でしょう。
しかし自分の仕業であれば、
わざわざそれを分かるような名を刻む事はいたしますまい」
と、取りなしてくれたので、なんとか太蔵は罪を逃れる事が出来ました。
このことがあってから、大蔵は城下から遠く離れた
深海(ふかみ)の里に移り住み、そこで多くの名刀を残したそうです。
そして山下淵の主は大蔵との約束を忘れていなかったのか
あれ以来、
山下淵でおぼれ死ぬ者は一人としていなかったということです。
おしまい

山下淵の大なまず(諫早・公園橋)
山下淵の大なまず その2
本日、2月11日は祝日「建国記念の日」。
この日は、戦前は「紀元節」と呼ばれており、
初代の神武天皇が葦原中国(日本)を平定され御即位された日を、
現行暦に合わせて算定した日である
2月11日を祝日としたものです。
いまこの時があるのは、様々な時代の中
先人の方々がご尽力された結果なのでしょう。
それらを振り返りつつ、感謝の気持ちを持っていたいものですね。
さて、先日のブログ「山下淵の大なまず」の続きです。
【山下淵の大なまず その2】
それから三日後の夜、その女性は再び大蔵のもとを訪れ、
大蔵の作った見事なモリを見るととても喜びました。
「ありがとうございます。これはほんのお礼のしるしです」
と、白い包みを渡しました。
何げなく開けて見ると、なんと銀の延べ棒だったのです。
大蔵は驚いて、押し返そうとしましたが、
「いいえ、どうかお受け取り下さい。あなたさまの立派なモリは、
この銀でも足りぬほどです」
「そうですか、そこまでおっしゃるのであればありがたく頂きます。
しかし、あなたは一体どなたですか?
そしてなぜ、このモリが必要なのですか?
もちろん他言は致しませぬゆえ、どうかお聞かせ下され」
大蔵が言うと、その女性はそっとあたりをうかがい、
声をひそめてこんな事を言いました。
「実はわたしは、お城の近くの山下淵の主なのです。
ところが近頃、大なまずがやって来ては、私の子どもたちを
次々と食い殺してしまいました。
この上は、憎い大なまずを殺して子どもたちの仇を討ちたいと思い、
あなたにお願いに来たのです」
「何と・・・」
大蔵が驚いていると、女は続けて、
「仇を討ったあかつきには、今後いっさい山下淵では、
人の命を取らぬ様に致します」
と、それだけ言って、すーっと姿を消してしまいました。
・・・・次回へ続く。

山下淵の大なまず(諫早・公園橋)
山下淵の大なまず その1
諫早神社の境内前を流れる諫早の母なる川、本明川。
この諫早に数多く残された伝説の一つで
本明川の「山下淵の大なまず」という伝説があります。
ご存知の方もいらっしゃるでしょうが
本明川は、北に聳える五家原岳南西麓を水源として
急斜面を流れ下り、様々な支流と合流しながら
有明海に注いでいる河川です。
日本でも有数の急峻な一級河川として知られています。
諫早神社もこの暴れ川・本明川の氾濫により
諫早大水害をはじめとして
これまでに何度となく多大な被害を被ってきました。
この本明川が、城山の岩崖にぶつかって淵を形成し、
山下淵と言われる所があります。
その昔はこの城山に高城が築かれており、
切り立った岩崖が今より広く深い淵に真っ直ぐ落ち込み、
自然の要害でもあったのでしょう。
「山下淵の大なまず」は
その本明川・山下淵を舞台とした伝説です。
【山下淵の大なまず その1】
むかしむかし今からもう四百年も前のこと、伊佐早(諫早)地方の領主
西郷純堯の時代、栄田村に中村大蔵(なかむらたいぞう)という、
腕の良い刀鍛冶がいました。
ある時、大蔵は神社へ納める神剣を作ろうと思いたちました。
そしてそれから百日の間、大蔵は水をかぶって身を清めると、
朝から晩まで一心に刀剣を打ち続けたのです。
そんなある日の事、一人の女性が大蔵のもとを訪れました。
「お願いがございます。どうか私に、鋭いモリを一本作ってもらえませんか」
「いや、今は打ち込んでいる仕事がありますので」
「お願いします。どうしても必要なのです。」
大蔵はびっくりして一度は断わったものの、
その女性があまりにも熱心に頼むので、ついに引き受ける事にしました。
「わかりました。それでは、三日後にまた来て下さい」
・・・・次回へ続く。

山下淵の大なまず(諫早・公園橋)