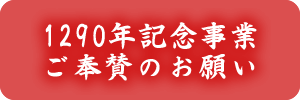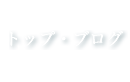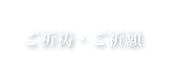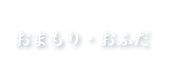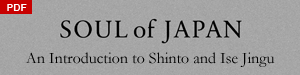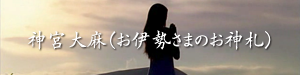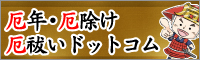-
最近の投稿
- 【 猫の日 ✕ ひな飾り 】 2026年2月17日
- 【 みんなでお祝いする豊かさ 】 2026年2月17日
- 【 この二日間限定 】 2026年2月17日
- 【 現代の神話 】 2026年2月17日
- 【 二万の和 】 2026年2月14日
記事の検索
記事カテゴリー
更新カレンダー
過去の記事
JR「ぶらり大村線」で紹介されました
本日は晴天にもかかわらず気温の上昇はあまり感じられず
春の一歩手前かなと思わせる天候となっています。
さて、JR九州の「ぶらり大村線」というサイトがあり
諫早市を紹介しているページに、モデルコースが提示されていて
その一番目に諫早神社が紹介されていました。
ちなみに、モデルコースは下記のルートです。
■諫早市ぶらりモデルコース(諫早歴史散策)
【所要時間】約60分 【距離】約3km
諫早神社(クス群)→諫早公園(眼鏡橋)→
高城神社(若杉春后霊神)→高城回廊(御書院)→
飛び石→慶巌寺(六段発祥の地)
モデルコースの詳しくはこちらをご参照下さい。
長崎県のほぼ中央に位置している諫早市は、
周りを有明海・大村湾・橘湾という
それぞれの特徴を持った海に面しており
豊かな海の幸と山の幸を楽しむことができます。
具体的には「伊木力みかん」や「諫早楽焼うなぎ」、
「小長井カキ」などがあります。
また、JR諫早駅は長崎駅に次いで
県内では二番目に乗降客が多い駅であり
非常に多くの方々が利用されている駅となっています。
ぜひお時間ある際には
諫早市を散策していただければと思います。
慰霊祭
先日、私を含め諫早支部の神職三名で
慰霊祭の奉仕をさせて頂きました。
雨天の中でのご奉仕となりましたが、心を込めて務めさせて頂きました。
複数神職でのご奉仕はあまり機会もないため、
大変貴重な経験となりました。
今後にも活かしていきたいと思っております。
募集中「日本人の心の故郷、神社を学ぼう!」
諫早駅前のお茶の間通り商店街の企画により
来たる3月13日(日)13:30から、ホテル・センリュウにおいて
「日本人の心の故郷、神社を学ぼう! ~身近な神社のお話~」と題した
講演会が開催されます。
この会のゲストスピーカーとして
御館山稲荷神社と諫早神社の神職が参加します。
諫早の歴史や神社のことなど皆さんの身近なことについて
お話しできればと思っております。
参加人数には限りがあり、申込みが必要です。
まだ応募できるそうですので
ご関心あられる方は是非ご参加下さい。
以下詳細です。
■講演名
「日本人の心の故郷、神社を学ぼう! ~身近な神社のお話~」
■主催
諫早駅前 お茶の間通り商店街
■日時
3月13日(日) 13:30~15:30 受付は13時から
■会場
L&L ホテル・センリュウ(諫早市永昌東町13-29)
■募集定員
50名
■参加費
500円 もしくは のんのこスタンプ満貼台紙一冊
(コーヒーとケーキが出されます)
■申込み・問合せ先
0957-21-1639
お茶の間通り商店街事務所
弥生3月1日「つきなみさい」
本日の3月1日「つきなみさい」も
予定通り滞りなく斎行いたしました。
次回の「つきなみさい」は
3月15日(火)
9:30~
となります。
皆様とともに
日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願いたします。
自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
■弥生(3月)歳時記
誕生石:アクアマリン
誕生花:スイートピー
開花:パンジー、ジンチョウゲ、アカシア
青果:キャベツ、サヤエンドウ、三つ葉、ウド、イチゴ
旬魚:サワラ、ニシン、マダイ、ハマグリ、ワカメ
『とっとって』260号で紹介されました
昨日夜から今朝にかけてしばらく雨が降りましたが
その後は落ち着いた空模様となっているようです。
さて、昨日2/27発行された
長崎新聞の日曜版生活情報誌『とっとって』に
諫早神社が紹介されました。
こちらの10ページに「杵の川」さんの蔵開きの特集が
組まれていて、その関連で当神社も掲載されています。

「杵の川」さんは諫早市唯一の酒蔵で、毎年この時期に
蔵開きを開催されています。
今年は平成23年3月19日(土)~21日(月)の三日間で
様々なイベントが行われ、入場無料です。
10:00~16:00まで、
JR諫早駅裏(西口)~杵の川間の
無料送迎シャトルバスも随時運行されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
栄田町公民館の竣工落成式
ここしばらくは春の陽気を感じさせる日差しが続き、
境内の梅の花も満開を迎えています。
さて、当社が兼務している栄田・歳神社のある諫早市栄田町では
既存の公民館が老朽化し手狭になったきたため、
昨年から新しい公民館の建設が進められ、昨日
竣工落成式が行われました。
昨年七月に地鎮祭、十月に上棟祭、
そして昨日竣工祭のご奉仕をさせていただき
大変立派な公民館が出来上がりました。

栄田町は、諫早駅が近く利便性が高いということもあり
この人口減少社会でも住人が増えているそうです。
新しく移り住む人が多いのですが、伝統芸能の「浮立」も伝承されています。
熟練の方々と子供たちが一緒に一生懸命練習し、
栄田・歳神社に奉納している「栄田町浮立」を
昨日の落成式でも皆さんに披露していました。
今後とも栄田・歳神社の御神徳が発揚されるよう
氏子の皆様とご協力しながらご奉仕するとともに
栄田町の益々の弥栄を祈念しております。
如月2月15日「つきなみさい」
社務所近くの梅の木にも蕾を確認することができ、
春の訪れを少しずつ体感できます。
さて、本日2月15日の「つきなみさい」が執り行われ
滞りなく斎行されました。
ご参詣いただきました皆様ありがとうございました。
次回の「つきなみさい」は、
3月1日(火)
午前9:30~ となります。
皆様とともに
日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願いたします。
自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
最後に、今後3ヶ月の「戌の日」をお知らせ致します。
安産祈願(着帯祝い)の時期目安としてご参考くださいませ。
如月 2月 24日(木)
弥生 3月 8日(火)、20日(日)
卯月 4月 1日(金)、13日(水)、25日(月)
皐月 5月 7日(土) 、19日(木)、31日(火)
如月2月1日「つきなみさい」
連日寒い日が続いておりましたが
今日を境に少しずつ春の装いになっていくようです。
さて、本日の2月1日「つきなみさい」も
予定通り滞りなく斎行いたしました。
次回の「つきなみさい」は
2月15日(火)
9:30~
となります。
皆様とともに
日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願いたします。
自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
■如月(2月)歳時記
誕生石:アメジスト
誕生花:マーガレット
開花:ツバキ、ウメ、ネコヤナギ
青果:ホウレンソウ、セロリ、ニラ、菜の花、ハッサク
旬魚:キンメダイ、メカジキ、ワカサギ、シジミ、アカガイ
平成23年「戌の日」 安産祈願
本日は新年となって二回目の「戌の日」ということもあり
安産祈願のご祈祷をご奉仕させて頂きました。
安産祈願(着帯祝い)は、
妊婦のお腹に木綿の布で作られた腹帯(ふくたい、岩田帯(いわたおび))を
巻き、安産と母子の無事を神社などに参詣し祈願することです。
安産祈願を、妊娠5ヶ月目頃の「戌の日」におこなうのは
犬はたくさん子を産み、その上お産が軽いことから
古来より安産の守り神として人々に愛されてきたことにあやかったものです。
腹帯は、妊婦に母親となることへの自覚を高めさせる意味があります。
また、胎児を保護し、胎児の霊魂を安定させるなどの意味も
あると言われています。
ただし、ご祈祷の時期は
必ずしも妊娠5ヶ月目頃の「戌の日」でなくとも、
お身体の安定している時期であれば
ご都合のつかれる佳き日を選んでお申込みいただいて結構でございます。
下記に今年の「戌の日」一覧をご紹介します。
時期の目安としてご参考くださいませ。
■平成23年(2011年) 戌の日一覧 ※ご参考
1月 7日(金)、19日(水)、31日(月)
2月 12日(土) 、24日(木)
3月 8日(火) 、20日(日)
4月 1日(金) 、13日(水) 、25日(月)
5月 7日(土) 、19日(木)、31日(火)
6月 12日(日)、24日(金)
7月 6日(水)、18日(月)、30日(土)
8月 11日(木)、23日(火)
9月 4日(日)、16日(金)、28日(水)
10月 10日(月)、22日(土)
11月 3日(木)、15日(水)、27日(日)
12月 9日(金)、21日(水)
睦月1月15日「つきなみさい」
改めまして、新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、平成23年はじめての「つきなみさい」が
昨日1月15日に執り行われ、滞りなく斎行されました。
ご参詣いただきました皆様ありがとうございました。
次回の「つきなみさい」は、
2月1日(火)
9:30~
となります。
皆様とともに
日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願いたします。
自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
最後に、今後3ヶ月の「戌の日」をお知らせ致します。
安産祈願(着帯祝い)の時期目安としてご参考くださいませ。
睦月 1月 19日(水)、31日(月)
如月 2月 12日(土)、24日(木)
弥生 3月 8日(火)、20日(日)
卯月 4月 1日(金)、13日(水)、25日(月)