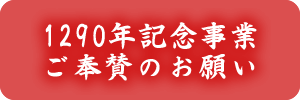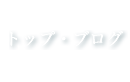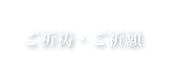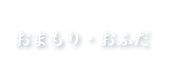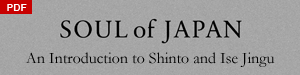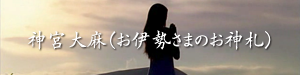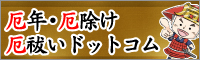-
最近の投稿
- 【 猫の日 ✕ ひな飾り 】 2026年2月17日
- 【 みんなでお祝いする豊かさ 】 2026年2月17日
- 【 この二日間限定 】 2026年2月17日
- 【 現代の神話 】 2026年2月17日
- 【 二万の和 】 2026年2月14日
記事の検索
記事カテゴリー
更新カレンダー
過去の記事
ハウステンボス 夏に向けリニューアル
本日も暑い一日となっておりますが
明日からは下り坂の天気が想定されており、
いよいよ梅雨の時期到来ということになりそうです。
さて、先日経営陣が刷新されたハウステンボスですが
夏に向けた事業展開ということで
リニューアル第二弾の内容が本日発表されました。
このリニューアル第二弾の要旨は以下の通りです。
●テーマパークゾーンが大きく充実
●昼も夜も楽しいハウステンボス
●家族やカップルから大人まで楽しめるパークへ
●フリーゾーンの利便性向上もスタート
具体的には
7/11(日)に園内のミュージアムスタッドが
フジテレビとタイアップし『スリラー・ファンタジー・ミュージアム』
として生まれ変わります。
例えば、
・ホラータウンを彩るイルミネーションショー、
・トリックアートやマジックショーが楽しめるメロディ・イン・ザ・ダーク、
・新感覚ホラーアトラクションのゴースト・ウエディング、
・マイケルジャクソンの展示やショーが展開されるMJワールド、
・ゲゲゲの鬼太郎の世界を体験できるスプーキー・ホール
・様々な占い師が集結するフォーチュン・チェンバー
・ホラーをコンセプトにした斬新なメニューのGMAレストラン
などがあります。
また、7/15~10/17の3ヶ月限定で
絶大な人気を誇る漫画「ONE PIECE」の世界を再現した
アトラクションやレストランなどが展開される
『ONE PIECE メモリアルログ in ハウステンボス』
という体験型イベントが行われます。
そして、清水国明氏プロデュースによる
日帰りバーベキューや手ぶらでのキャンプが楽しめる「キャンプテンボス」、
アムステル運河における釣堀「シーテンボス」、
水と炎をテーマにしたサンバやタヒチアンダンスが繰り広げられる
「サマービート」、「ミッフィーワールド」、「宝探し」、
世界の花火師が集合する「第2回世界花火師競技会」なども行われます。
このように、これまでのハウステンボスとは一味違った内容の
リニューアルが行われる予定となっています。
果たしてこのリニューアルが多くの方に受け入れられるのか。
大きな期待を抱きながらこれからの展開を見守りたいと思います。
心配な状況が続く口蹄疫
本日も外作業をしている際に汗が流れ落ちるような
暑い一日となっています。
さて、宮崎県で発生している家畜伝染病の口蹄疫について
問題がおさまりつつあるかと思っていましたが、
昨日今日で都城市、宮崎市、日向市、西都市でも
新たに感染や感染の疑いが発生しています。
報道ベースでしか現地の状況は把握できませんが
現場の方々のご心配、ご苦労、ご努力、恐怖は
想像を絶するものだと思われます。
われわれにできることは限られていますが
できることはしていきたいと思っております。
なんとか被害が最小限に抑えられるよう
早期の事態鎮静化を願うばかりです。
新総理ゆかりの神社?
本日も汗ばむような暑さとなり、
夏の入口を感じさせます。
さて、その時々の時事ネタに関わる神社がある場合、
その神社への関心が高まることは多々あるようです。
今回、国政における突然の政変により誕生した
菅直人首相に関わりのある神社があるとのことで、
その神社への注目が高まり
参拝客が増えたり取材が殺到するなどしているようです。
その名も、京都市下京区に鎮座する
「菅大臣神社(かんだいじんじんじゃ)」です。
この菅大臣神社は、学問の神様として知られる菅原道真公を
ご祭神とし、建立時期は道真公没後すぐの平安時代とされ
道真公の旧宅跡とされる場所に建っているという。
この神社に、菅首相が初めて訪れたのは平成15年10月。
当時、民主党の代表だった菅氏は
11月に行われる衆議院選挙の「必勝祈願」で訪れ、
その後も、お忍びで当選のお礼参りに再び訪れたとのこと。
残念ながら、それ以降は参拝に訪れたことはなく
今後の参拝も今のところ予定はないそうですが
ぜひ総理として神前にて誓いをたてていただきたいものです。
いずれにしろ、総理に就任したからには
日本の国の舵取りをする気概と責任を自覚し
間違った方向に進まないようにしていただかないと困ります。
パワースポット ミステリーツアー
本日も暑い暑い一日となっており、
日曜までは同じような天気が続くようです。
さて、間もなく22:55~ NHKの『爆笑問題のニッポンの教養』で
「京都パワースポット ミステリーツアー」と題した番組があります。
この番組では
現在のパワースポットブームに着目します。
今、清正井に東京大神宮、九頭竜神社に江島神社、高尾山に
富士山まで、幸運をもたらすとされる場所には、
婚活や就活の成功を願う人々が若い女性たちを中心に
列をなしている状況がある。
そこで、なぜ人は見えないものにパワーを感じ、すがるのか?
そもそもパワースポットとはどんな場所なのか?
を探究する。
爆笑問題が、その答えを求めて
妖怪・魔界研究の第一人者である国際日本文化研究センターの
小松和彦教授を訪ね、春の京都を訪ねる。
小松教授は、鬼、異人、闇、呪い、妖怪など
日本文化史研究において隠蔽されてきた「負」の部分を分析して、
日本人、日本文化の内奥の謎に迫っている方だそうです。
番組が向かう先は、“京都有数の心霊スポット”など。
「パワースポットは元々神仏や妖怪、鬼のすむ異界と人間界との
接点である“鬼門”。 神や仏だけでなく魔物や鬼のパワーも
集まる、危険な場所とも言えるんです」と小松教授。
徐々に明らかになるパワースポットの真実。
やがて日本人の心の奥底に潜む、
独特の世界観が浮かび上がってくる。
はたして最強のパワースポットは、どこなのか?
という予告をみて、
特に「日本人の心の奥底に潜む、独特の世界観」という点に
興味を覚えたので
この番組を見てみようと思います。
サッカー日本代表シンボルマーク:八咫烏
本日も穏やかな日差しに包まれた一日となっています。
もうすぐ梅雨の季節がやってきますが
まだしばらく雨の心配はなさそうです。
さて、サッカーのワールドカップ南アフリカ大会が
いよいよ今週金曜の6/12~7/12の日程で開催されます。
大会前の強化試合などではコンディション調整不足なのか、
連係や個人技の面でも心許ないように映りました。
本番ではぜひ持てる力の全てを発揮してほしいものです。
そのサッカー日本代表のシンボルマークをご存知でしょうか。
一度は見たことがあると思いますが
この黒い鳥、じつは3本足のカラスで「八咫烏(やたがらす)」と言います。
この「八咫烏」は、
日本神話で、タカミムスビによって神武天皇の元に遣わされ
熊野国から大和国への道案内をしたとされる鳥です。
さらに世界遺産にも登録された熊野本宮大社、熊野速玉大社、
熊野那智大社の熊野三山においては
「八咫烏」は太陽の化身・神の鳥として祭られているのです。
では、なぜこの「八咫烏」が
サッカー日本代表のシンボルマークとなったのか。
それは、日本に初めて近代サッカーを紹介した中村覚之助氏に
敬意を表して、中村氏の出身地である那智勝浦町にある
熊野那智大社の八咫烏をデザインし、
日本サッカー協会がこれをシンボルマークとしたのだそうです。
6/14カメルーン戦を皮切りに、6/19オランダ戦、6/24デンマーク戦と
グループEの厳しい予選が繰り広げられます。
果たしてサッカー日本代表は
この「八咫烏」のパワーを力にして勝利を積み重ねることができるでしょうか。
【ご案内】夏越の大祓式 6/27(日)16:00~
本日は「戌の日」と土曜日が重なっているということもあり
安産祈願(着帯祝い)のご祈祷が多い一日となりました。
どうぞこれからもご自愛いただき安静にお過ごしになって下さい。
さて、先日より通知しておりましたとおり
「夏越の大祓式」斎行の詳細をご案内申し上げます。
■平成22年 夏越の大祓式
日時:6/27(日)16:00~ 所要時間:約30分
場所:諫早神社境内
※自由にご参列できますので、どうぞご参集下さい。
なお、雨天の場合も決行致します。
※本初穂料は300円ほどお心持ちでお納め下さい。
※ご参列できない方も
社頭にて事前に大祓の人形(ひとがた)を頒布しておりますので、
人形をお持ち帰りいただき、当日6/27までに社務所へお納め下さい。
お納めいただいた人形は大祓式の神事でお清めお祓いをし、
全てお焚き上げ致します。
※「茅の輪」の設置期間は、6/20頃~7/3頃を予定しております。
【大祓式とは】
私たちは日常生活の中で知らず知らずのうちに人を傷つけたり、
罪を犯したり、穢れに触れています。
そして、その状態を放っておくといずれ大きな災厄となって
降りかかってくると云われています。
この大祓式の神事は
それらの「罪」「過ち」を取り除き、
体内に生じた「けがれ(=気枯れ)」を人形(ひとがた)に託して
祓い除けるという日本古来の伝統的な行事です。
毎年6月と12月の末に行われ、6月を「夏越の大祓式」、
12月を「年越の大祓式」といいます。
特に6月末の「夏越の大祓式」では
心身を清めるための「茅の輪くぐり」を行います。
【歴史】
その歴史は古く、平安時代に大宝律令で正式な宮中行事と定められ、
中世より全国に普及し、現在も多くの神社で行われています。
なお、文書で残っているものが手元になく定かではありませんが、
当神社ではずっと斎行できずにいたため
数十年の時を超え、約百年ぶりに「大祓式」の復活となります。
【茅の輪】

「茅の輪」とは茅草等で作られた大きな輪のことで
これをくぐることにより、疫病や罪穢が祓われるとされています。
くぐり方は、
「水無月(みなつき)の夏越しの祓する人はちとせの命のぶというなり」
という古歌を唱えつつ、左まわり・右まわり・左まわりと、
八の宇を書くように三度くぐり抜けます。
こうして心身ともに清らかになり、
あとの半年間を新たな気持ちで過ごすことができるのです。
芽の輪の起源については、善行をした蘇民将来(そみんしょうらい)が
武塔神(むとうのかみ)から
「もしも疫病が流行したら、茅の輪を腰につけると免れる」といわれ、
そのとおりにしたところ
疫病から免れることができたという故事からきています。
【人形(ひとがた)】

大祓では、身代わり人形に託して、これまでの罪穢れを祓い除けます。
①各人それぞれが自身の全身を人形で丁寧になでます。特に病ん
でいる部分などがあれば、より丁寧になでるとよいでしょう。
②最後に、その人形に「フーッ」×3、と息を3度吹きかけます。
こうすることで、自分に積もっている罪や穢れ、身体の悪い部分が
人形に移ると云われています。
それらが人形に乗り移るよう祈念を込めましょう。
このように、その年々の節目におこなわれる大祓は
罪や穢れを祓うとともに、自らを振り返るための機会となります。
大祓式により、清浄な心身で残りの半年を過ごしましょう。
平成22年神社庁神職総会
本日は昨日に続き、長崎県神社庁にて
「平成22年神社庁神職総会」に参加してきました。
神殿祭、表彰式、神職総会ののち
「教化モデル神社」の活動報告、そして直会が行われました。
じつは私としては初めての参加だったため
全てが新鮮に感じ、様々な発見がありました。
個人的には特に「教化モデル神社」の活動報告が
大変参考になりました。
二つの神社の活動報告があったのですが、
当神社ではなかなかできていないような様々な活動をされていて
学ぶべきことがたくさんあり、強い感銘を受けました。
どの世界も言えることですが
全体を底上げするには、その全体を構成する各々の個がレベルアップして
はじめて全体の底上げにつながるものです。
当神社も一神社として研鑽を積み
本日学ばせていただいたこと等を今後活かしながら
神社界の発展に貢献していくことができれば幸いです。
物故神職慰霊祭
本日も夏を思わせるような陽気となっています。
さて、本日は県神社庁にて「物故神職慰霊祭」が斎行され
参列して参りました。
これは、これまでにお亡くなりになられた長崎県の神職の
御先祖様に対する御霊和めの神事です。
今回、当神社の宮司が本年亡くなったということもあり
ご案内を頂き、私は遺族として玉串拝礼もさせて頂きました。
神社庁長・斎主・斎員の方々をはじめ
多くの方々のご参列のもと慰霊の誠を捧げていただき
深く感謝申し上げます。
愕然
本日も朝から温かく晴れやかな天候でしたが
天気予報どおり、夕方からは雨が降ってきました。
さて、日本はどこへ向かってゆくのでしょうか。
具体的なことは申しませんが、
国や地方の財政のしくみを理解すれば、もう待ったなしの状況です。
また、財政に限らず、教育や経済あらゆる面で
はっきりとした将来展望を持った道しるべを
いま歩まなければ、ジリ貧になるのは間違いありません。
そして、ほとんどの報道が政局がらみのものであることも
正直愕然としました。
いま私たちが考える材料としなければならないのは一体何なのでしょうか。
「だれが」「どこの党が」ではないのです。
国民不在の「政局」では何も解決しません。
私たちは
目の前のことや甘い言葉に誘惑されても自制しなければなりません。
今日までのことでわかったでしょう。
それは結局、私たち自身にそのツケが跳ね返ってきます。
将来ビジョンのある政策、裏付けのある政策、そして国益を考えた政策、
これらを実行できる人がリーダーになってほしいものです。
水無月6月1日「つきなみさい」
本日も穏やかな天候で
そのまま一日が終わるかと思っていましたが、
15時過ぎ頃からでしょうか、突然雷が鳴り響き
強い雨が降ってきました。
通り雨かと思ったところ、いまだ雨が降り続いています。
早く回復してほしいものです。
さて、本日の6月1日「つきなみさい」は
滞りなく斎行いたしました。
いつもよりも多くの方々にご参詣いただき
ありがとうございました。
次回の「つきなみさい」は
6月15日(火)
9:30~
となります。
皆様とともに
日々の神恩感謝や健康安泰・繁栄などを祈願いたします。
自由にご参列できますので、
ご都合つかれる方はどうぞご参詣下さい。
■水無月(6月)歳時記
誕生石:パール
誕生花:バラ
開花:ショウブ、ツキミソウ、ユリ、アヤメ
青果:トマト、スイカ、ビワ、モモ
旬魚:アユ、スズキ、シジミ、ワカメ